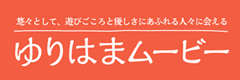本文
介護保険料について
介護保険は、介護を必要とする方のための費用や、介護が必要な状態になることを予防するための費用を、社会みんなで負担し合う制度です。皆さまに納付していただく保険料は、制度を維持していくための大切な財源となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
40~65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
第2号被保険者の保険料は、それぞれ加入している国保や健康保険などの医療保険と併せて納めていただくことになっています。詳しくは、各医療保険者へお問い合わせください。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
第1号被保険者の保険料は、介護保険事業計画・高齢者福祉計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
介護保険給付にかかる費用と65歳以上の人数などから算出した「基準額」をもとに、本人と世帯の課税状況や所得に応じて段階的に決められます。
令和6年度~令和8年度までの基準額は、年額80,900円(月額6,740円)です。
令和6~8年度の保険料額一覧表
| 段階 | 対象者 | 計算方法 |
年間 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 段階 |
本人が 町民税非課税 |
世帯全員が 町民税非課税 |
生活保護受給者または老齢福祉年金受給者 |
基準額×0.285 |
23,000円 |
|
前年中の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
|||||
| 第2 段階 |
前年中の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 |
基準額×0.485 |
39,200円 | ||
| 第3 段階 |
前年中の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計が120万円超の方 |
基準額×0.685 |
55,400円 | ||
| 第4 段階 |
世帯に 町民税課税者 がいる |
前年中の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.9 |
72,800円 | |
|
第5 |
前年中の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80万円超の方 |
基準額 | 80,900円 | ||
| 第6 段階 |
本人が町民税課税 |
前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
97,000円 |
|
| 第7 段階 |
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 |
105,100円 |
||
| 第8 段階 |
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 |
121,300円 | ||
| 第9 段階 |
前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.7 |
137,500円 | ||
| 第10 段階 |
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 153,700円 | ||
| 第11 段階 |
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 169,800円 | ||
| 第12 段階 |
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 186,000円 | ||
| 第13 段階 |
前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 | 基準額×2.4 | 194,100円 | ||
| 第14 段階 |
前年の合計所得金額が820万円以上1000万円未満の方 | 基準額×2.5 | 202,200円 | ||
| 第15 段階 |
前年の合計所得金額が1000万円以上の方 |
基準額×2.6 |
210,300円 | ||
※上表第1段階~第3段階に該当する低所得者の高齢者については、公費(国・県・町が負担)による保険料の軽減を図っています。
老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金
課税年金収入額
市町村民税の課税対象とされる公的年金等の収入金額(※遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などは含まない)
合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額
保険料の納め方
65歳以上の方の介護保険料は、年金を受給されている方の場合、原則として年金から介護保険料があらかじめ差し引かれます(特別徴収)。しかし、年金が少額の場合や年金を受給していない方の場合は、納付書または口座振替により納めていただくことになります(普通徴収)。
普通徴収について、詳しくはこちら「各種税金の納付方法」
年度途中で65歳になる方は
65歳になられた年度の介護保険料は、誕生日の前日の属する月より、月割で算定します。
(例)4月1日生まれ→3月31日に65歳到達・・・3月分から介護保険料を納付
4月2日生まれ→4月1日に65歳到達・・・4月分から介護保険料を納付
年度途中で65歳になられた方は、年金をすでに受給されていてもすぐに年金天引きが行えません。日本年金機構等で年金天引きの手続きが整うまでの間(半年~1年)は、納付書または口座振替で納めていただくことになります。
保険料の減免について
火災や天災などで財産に大きな被害を受けた場合や、疾病や失業などにより特に生活が困難と認められる場合には、申請によって介護保険料が減免になる制度があります。詳しくは町民生活課賦課徴収係へお問い合わせください。
介護保険料を滞納した場合
納期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書、電話催告などにより自主納付を促していますが、それでも納付に誠意が見られない場合には、公平性を保つために、財産調査を行い差押え等の滞納処分を執行します。
また、災害などの特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納していると、次のような措置が取られます。保険料は納め忘れのないようにしましょう。
1年以上滞納した場合
利用したサービスに係る費用の全額をいったん自己負担し、後日申請することで保険給付分が払い戻されます。
1年6か月以上滞納した場合
利用したサービスに係る費用の全額をいったん自己負担し、後日保険給付分の払い戻しを申請しても、一部または全部が一時的に差し止められます。
2年以上滞納した場合
保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担の割合が引き上げられます。また、高額介護サービス費なども支給されません。