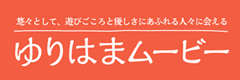本文
主な財政用語(その他)
| 用語(読み) | 意味 |
|---|---|
| 経常収支比率 (けいじょうしゅうしひりつ) |
財政構造の弾力性(ゆとり)を判断するための指標です。 地方税・普通交付税など、使いみちを制限されない毎年収入される収入(経常的な収入)に対する、人件費・公債費・扶助費など毎年支出される経費(経常的な支出)の割合です。この割合が低いほど、財政にゆとりがあり、さまざまな状況の変化に柔軟に対応できることを示します。80%を超えると、財政構造は弾力性を失いつつあると考えられ、厳しい財政運営を強いられることになります(財政の硬直化)。 ちなみに全国的には最小の都道府県でも85%くらいです。 |
| 公債費比率 (こうさいひひりつ) |
一般財源のうち、公債費(町の借金返済にあてる経費)に割り当てられた額の、標準財政規模に対する割合です。この数値が高いほど、財政構造の硬直性の高まりを示しています。 財政運営上、10%を超えないことが望ましいとされています。 |
| 起債制限比率 (きさいせいげんひりつ) |
財政の健全性を確保するため、公債費(町の借金返済にあてる経費)による財政負担の割合を判断し、地方債の発行を制限するための指標です。 平成17年度までは20%を超えると、町債の借り入れが一部制限されていました。 |
| 公債費負担比率 (こうさいひふたんひりつ) |
公債費と一般財源の関係を見るための指標です。 公債費(町の借金返済にあてる経費)に割り当てられた一般財源の額が、一般財源総額に占める割合で表します。この数値が高いほど、財政運営の硬直性の高まりを示しています。一般的には、財政運営上15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。 |
| 財政力指数 (ざいせいりょくしすう) |
地方公共団体の財政力の強弱をあらわす指標です。1を超えれば自前の収入で標準的な行政を行うことができるとみなされ、地方交付税は交付されません。 (基準財政収入額)÷(基準財政需要額) 基準財政収入額、基準財政需要額ともに地方交付税を客観的・合理的に算定するために、標準的な税の徴収を行い、標準的な行政を行ったという前提条件のもとに算出したものです。 基準財政収入額は住民税、軽油引取税、自動車取得税等の収入見込みの75/100、地方譲与税、交通安全対策特別交付金などで算定されます。 基準財政需要額は地方公共団体が合理的・妥当な水準の行政を行う際に必要な経費を福祉、教育など様々な行政分野ごとに算定して合算したものをいいます。 |
| 実質収支 (じっしつしゅうし) |
何らかの事情で未完成のため翌年度に繰り越された工事代金など、翌年度以後の支出財源となる金額分を除いた歳入から、歳出を引いた差額が実質収支です。 今年度の歳入には、前年度の実質収支も繰越金として引き継がれているため、今年度の実質収支から前年度の実質収支を引いた金額が単年度収支です。 また、歳入、歳出には基金への積み立てや取り崩し、地方債の繰上げ償還が含まれているので、そういった収支を調整する要素を除いた収支を実質単年度収支といいます。 なお、実質収支のマイナスが市町村は20%を超えたら、財政再建団体の対象になります。 |
| 実質公債費比率 (じっしつこうさいひひりつ) |
「平成18年度から地方債が許可制度から協議制度に移行したことに伴い、地方公共団体の普通会計での借金返済だけでなく、公営企業会計での借金返済や一部事務組合での借金返済に対する負担も加味して、そのすべての負担に賄われている一般財源が標準財政規模に占める割合を算定したものです。民間企業における連結決算の考え方を取り入れた財政指標といえます。 18%を超えると借金に当たって許可が必要となり、公債費負担適正化計画を策定した後でなければ新規借り入れは許可されず、25%を超えると一定の種類の新規借り入れは許可されません。 |
| 一般財源 (いっぱんざいげん) |
使いみちを特定されず、どのような経費にも使用することができる財源です。町税、地方譲与税、地方交付税、地方特例交付金などがこれにあたります。 |
| 特定財源 (とくていざいげん) |
補助金のように使いみちが特定されている財源です。国庫支出金、県支出金、町債などがこれにあたります。 |
| 一時借入金 (いちじかりいれきん) |
町の支払資金が一時的に不足した場合に借り入れるもので、いわゆる回転資金です。借入の限度額を予算に定めるとともに、その年度の歳入をもって年度内に返済しなければなりません。 |
| 基金 (ききん) |
特定の目的のために積み立てた資金や維持する財産、または定額の資金を運用するために設ける資金や財産のことです。財政調整基金、減債基金などがあります。 |