第二章 衣・食・住
第三節 住居
一 屋敷と家
本宅
本宅とは母屋のことをいう。農家の本宅は平屋、草ぶきであった。間取りは田の字型が一般的で、少し大きな家になると中の間、料理間などがついた。
戸の口(玄関)に面した奥の間をおもて(舎人地区ではでい)と呼び、床や仏壇を据え、主人の居間とした。冠婚葬祭の場でもあり、特別な客もここで接待した。夜は主人夫婦の寝室となった。
座敷は一般来客用の接待の場であった。しかし、機織り機を置いたり、蚕を飼う蚕室にしたりする場合もあった。
部屋は夫婦の部屋であり、特別な用件がない限り他の出入りは遠慮した。一番隅の部屋で採光が悪く、薄暗いことが多かった。
居間は家族団らんの場であった。食事をしたり、いろりを囲んで子供を交えて話し合ったり、針仕事や他の夜なべ仕事をしたりした。
戸の口は、大戸にくぐり戸が取り付けてあった。普段はくぐり戸で出入りしたが、大事〈おおごと〉や農作物を持ち込む際には大戸を開けた。
にわは土間で、穀物のこなしや冬のワラ仕事、夜なべの場に使用された。片隅にはワラ打ち石が据えられていた。にわの下手にはまやを設け、牛を飼っていた。牛は家族と同様に扱われ、家人が出入りする際に様子がよく分かるよう内まやにまっていた。
まやの後はにわのく(にわの奥)で、漬物やみそ・しょうゆを保存する場所であった。薄暗く、塩分でジメジメしていた。
 |
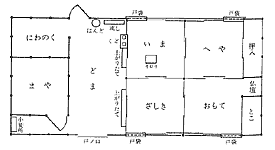 |
わら屋根の民家 (長和田・鹿田安信宅) |
図2農家の一般的な間取り |