第2章 指定文化財
第4節 町指定の有形文化財
小銅鐸
昭和5、6年ごろ、漆原の小林虎蔵(故人)が北福の字「北山」の丘陵地を耕起中に発見したものである。鋳銅製で、質は比較的良好であり、暗緑色を呈している。
総高9.25センチメートル、うち鐸身7.6センチメートル、鈕〈ちゅう〉(つまみ)部1.65センチメートル、重量213グラムである。身の横断面はほぼ円形で、底部の径5.2センチメートル、鈕のある上面の径3.0センチメートル、身の厚さ0.2〜0.36センチメートルで、鈕の厚さもほぼ同様である。文様はない。身の上半部に長方形の穴4個、上面に鈕を挾んで長方形と円形の穴がある。
銅鐸〈どうたく〉は弥生時代の青銅器の1つで、祭祀用に用いられたものとみられている。小さいものから150センチメートルぐらいのものまであるが、20センチメートル以下のものは小銅鐸と呼び区別されている。
参考 名越勉・甲斐忠彦報告「鳥取県東郷町出土の小銅鐸」
(『考古学雑誌』第五九巻第二号所収)
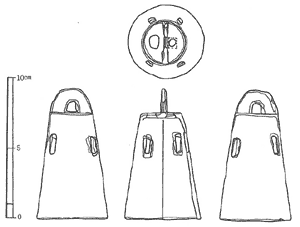 |
図3北福の小銅鐸実測図 (『倉吉市史』による) |