第2章 指定文化財
第4節 町指定の有形文化財
野方廃寺跡出土瓦
7世紀中期の創建とされる野方廃寺及び弥陀ケ平廃寺跡から出土した遺瓦のうち、町教育委員会所蔵のものが町の文化財に指定されている。内訳は軒丸瓦3個、丸瓦1個、軒平瓦1個、平瓦2個及び鴟尾〈しび〉片6個である。軒丸瓦は、いずれも複弁六葉蓮華文を持ち、7世紀後半から8世紀前半にかけてのものとみられる。このうち、ほぼ完全な形をとどめる1個は直径約18センチメートルで、中房(内部の円内)に7個の蓮子(ハスの実をかたどったもの)が配されており、外縁には、1本の圏〈けん〉線(囲いをした線)上に新羅〈しらぎ〉系の特徴である珠文が見られる。胎土はやや黒味がかる。
軒平瓦は四重の弧文〈こもん〉を持つ三重弧文が普通とされるが、地方によって、また、時代が下るにつれてその数に差異が見られるという。平瓦には布目が見られる。
鴟尾は須恵器質で堅く、丁寧に焼き上げられている。破片の数が少ないため、完形の推定は困難であるが、2メートル近くあったものと思われる(以上、倉吉市・真田広幸の提供資料によった)。
このほかに、県立博物館及び野方区民などが所蔵する遺瓦がいくつかあるが、町の文化財には指定されていない。
 |
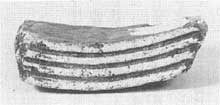 |
|
町教育委員会所蔵の野方廃寺出土の 軒丸瓦外縁に珠文が見られる (8世紀前半と推定) |
野方廃寺出土の四重弧文を持つ軒平瓦 (東郷町教育委員会所蔵) |