第四章 近代・現代
第九節 学校教育
二 各学校の沿革
(五) 東郷実科専修学校
○昭和十七年三月三十一日、東郷実科専修学校の設立認可が下りた。開校式は同年四月十一日に行っている。校区は舎人・東郷・松崎・花見及び泊の五か村であった。当初は、東郷国民学校の校舎が使用された。兵器などの器具は、各村の旧青年学校から持ち寄って使用した。当時、県内では各村の青年学校が数か村連合の組合立に統合されている。その校名のほとんどが「○○青年学校」となっているのに対して、本校のように実科(業)専修学校と称したのは県下六六校中八校であった(昭和二十年現在の公立校のみ・『鳥取県教育史』)。農業実習などを目的とするものであることを、校名により明らかにしようとしたもの、といわれる。
なお、東郷実科専修学校は前述したように、青年学校に相当する第一部と、全日制の第二部(充実課程)に分かれていた。しかし、同校の「沿革又ハ重要事項録」に記録された学校行事などの内容は、両部のいずれとも判別できないものが多い。
○同十八年五月、小鹿谷の報国農場五アールを開墾し、サツマイモと大豆を作付けした。また、川上の水田約一八アールを借り入れて耕作した。この結果、サツマイモ約五〇〇キログラム(うち供出三六〇キログラム)、米一二俵(同一一俵)を収穫した。また、同年十二月には、麻畑の炭窯を使って木炭を作っている。
○同十八年六月・久見字「向畑」(現・東郷中学校のある場所)の九〇アールに校舎を建築し、移転することになった。建物は、倉吉市の個人所有の養蚕場(瓦葺二階建て、一六・四間)一棟と、トタン葺平屋建て(七×二間)の物置を買収して移築した。養蚕場が校舎に、物置が農具舎に充てられた。校地の地ならしなどの作業には、同校職員や生徒が協力した。同年九月十日の鳥取大地震以後、資材の調達が難しくなって工事が遅れたという。新校舎に移転したのは、翌十九年一月であった。しかし、教室の床板の半数以上はまだ張られていなかった。同校の「沿革又ハ重要事項録」には、「寒風容赦〈しゃ〉ナク突破ス」と記されている。
○同十九年四月、教育充実のため、毎朝の朝礼の前後に課外教育を実施した。
○同年七月二十九日、大山までの長距離行軍を実施した。同日夜に町内を出発し、翌朝大山寺に到着した。三十一日に大山に登り、同日帰校した。
○同二十年一月、充実課程(第二部・全日制)の生徒に、三月末までの学徒勤労動員の命令が下った。中等学校(旧制中学校や実業学校など)の生徒と同一の扱いであった。
○同年二月、東郷村勤労学級が開設された。対象者など詳細は不明である。
○同年三月、食糧増産のため、教練場六アールを掘り起こした。また、四月には、山林の伐採跡地四〇アール弱(場所は不明)を開墾、校庭約一〇アールを掘り起こし、耕作した。
○同年十二月、銃二三九、剣一九八、軽機関銃五、擲〈てき〉弾筒五の教練器材を倉吉警察署に提出した。
○同二十一年一月、列車が制限されたため、泊村の生徒の通学が困難となり、毎週日曜日、教員が泊村に出張して教授した(三月まで)。また、同月、生徒の教科書を集め、焼却あるいは倉吉警察署に提出した。
○同年三月二十日、卒業式が行われた。本科卒業生一一人、第二部修了生九人であったが、全員女子であった。同年三月一日現在と前年八月の終戦当時の生徒数を表77に示した。両者を比較すると、終戦後に本科の男子一三六人、女子九〇人が増えている。
○同二十年度の同校の農業経営状況を紹介する。
農業 普通畑六〇アール、校庭の耕起や道路ばたの利用一〇アール、開墾地四〇アール
生産 米一五俵、麦五俵、サツマイモ六・七トン、ジャガイモ二・一トン、大豆七俵、大根六・七五トン、カボチャ〇・五トン、キュウリ〇・二トン、ナス〇・二トン、春大根や白菜など〇・六トン、キャベツ一・三トン、ジャガイモの種いも七五キロ、サツマイモの苗七万二〇〇〇本
○同二十一年、七月、畜舎で乳牛の飼育を始めた。
○同年八月、学校組合から泊村が離脱した。
○同二十二年四月、同校と東郷小学校の一部を借りて東郷中学校が開校した。
○同二十三年三月、本科卒業生九人、研究科修了生五人、第二部修了生三一人を送り出して廃校になった。
〔校長〕(1)小椋留一(昭和一七年三月〜) (2)浅村忠晴(同二二年四月〜)
 |
 |
|
東郷実科専修学校の印影 (昭和18年の修了証書から複写) |
東郷実科専修学校充実課程の第一回修了生 昭和18年3月(倉吉市・小椋留一提供) |
表77 東郷実科専修学校の生徒数 |
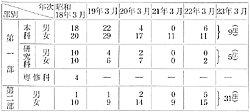 |
 |
東郷実科専修学校の畜舎と乳牛 昭和22年3月。同校職員のスナップ写真(倉吉市・小椋留一提供) |