第四章 近代・現代
第九節 学校教育
二 各学校の沿革
(一) 舎人小学校
舎人小学校
○明治二十三年七月、校舎を漆原から方地一〇五四番地に移転し、校名を舎人簡易小学校と改めて開校した。この時、松崎小学校の校区とされていた宮内・藤津は、舎人校の校区に復帰した。新校舎の規模などは明らかでない。建設場所の選定に当たっては、通学距離などが問題にされ、宮内・藤津と他の六か村の間で白熱した論議が行われたという。前記の場所は、現・町役場倉庫(旧・公民館東会館、旧農協舎人支所)の付近である。
○同年十二月、補習科が併設された。
○同二十四年四月一日、舎人尋常小学校と改称した。
○同二十五年十一月二十五日、改正小学校令によって開校式を行った。
○同三十二年二月一日から一か月間、宮内の一・二年生のための臨時の分教場が同地の薬師庵で開設された。明治三十五年まで毎年開設されている。
○同年十二月、裁縫科を加設した。
○同三十四年一月、校舎改築を審議するための村議会が開かれた。就学児童数の増加で、校舎が手狭になったためである。しかし、校舎の敷地を変更するかどうかで、同二十三年の場合と同様の論争が起こった。宮内・藤津は藤津字「八津」付近を、他の村は方地字「小清水」付近を主張したという。学務委員が調停に乗り出し、四昼夜の交渉を重ねた結果、敷地は変更しないことで決着した。三十四年三月、校舎用に長和田の個人所有の機業場を八七五円で購入した。七×四間の総二階であったという。同年十二月に増築校舎の落成式を行っている。
○同年四月、校旗を作成した。舎の字に、つぼみをもつ二本の茎を配した図案であった。白羽二重の地に、絹の色糸で刺しゅうを施したという。現物は残っていないが、「舎人小沿革史」によると、舎の字が赤、茎が緑、つぼみの先端と葉の部分が朱である。
○同三十六年八月、運動場がなかったため、その造成工事に着手した。同校の沿革史には、校舎の西南隣の田地を借りて運動場とした、と記録されている。しかし、後述する昭和十五年当時の運動場は、旧・町公民館東会館から県道沿いの泊村側一帯、すなわち校舎の北東隣である。運動場がその後移転したものであろうか。校舎と併せて、その変遷の状況は不明である。
○同三十九年二月、校訓が制定された。当時の校長・保田堅治の作であった。「越天楽」の節回しで、毎朝の朝礼で児童に唱和させたという。
校訓
恥をば知りて辛抱し 心誠に親切に 天皇〈すめらみこと〉の御教〈みおし〉えを 朝な夕なに守るべし
○同四十一年十二月、二階建ての校舎一棟を建築した。広さは四×八間であった(町役場所蔵「財産台帳」)。
○同四十三年から、卒業記念写真の撮影が始まった。同年には尋常科六年課程の初の卒業生を送り出している。
○大正六年四月、舎人農業補習学校が併設された。
○同七年四月、高等科を設け、舎人尋常高等小学校となった。
○同十二年五月、新しい二階建ての校舎が完成した。一階が講堂(体育館)であった。
○同十五年六月、舎人青年訓練所が舎人農業補修学校に併置された。
○昭和四年四月、児童(五年生以上)の自治会総会を開催した。また、全学級の級長を任命している。
○同年八月、運動場に隣接して奉安殿を築造した。
○同六年四月、農業補修学校と青年訓練所が統合され、新たに舎人農業公民学校が併置された。
○同八年十一月、校舎の増改築工事が完成した。増築された校舎は、前掲「財産台帳」によると、木造瓦葺〈かわらぶき〉二階建て一棟(五・五×一六・五間)と、同一棟(六×六間)などであった。
○同十年四月、舎人農業公民学校が舎人村青年学校と改称した。
○同十二年、青年学校専用の教室(一室)を設けた。
○同十五年十月、運動場に隣接して記念教育館(五・五×四間)を建設した。この年は、神武天皇の即位から数えて二六〇〇年、教育勅語の下賜から五〇年に当たる記念の年であった。当時の校舎配置図を示した。教育館は、児童や各種団体の修養道場として使われたという。このほか、野方などに二〇アールの報国農場を設置している。なお、教育館は後に舎人村公民館に充てられ、さらに野花の旧・公民館に使用された。
○同十六年四月、舎人国民学校と改称した。
○同二十一年七月、舎人少年団が結成された。
○同年八月、奉安殿を撤去した。
○同二十二年四月一日、舎人小学校と改称した。
○同年十二月、PTAの創立総会を開催した。
○同二十六年八月、校長住宅一棟(木造平屋建て・二一坪)を新築した(前掲「財産台帳」)。
○同二十七年十一月、校舎の改築工事が完成した。この時、二階建ての講堂を平屋建て(六×一一間)にした(前掲「財産台帳」)。
○舎人小学校の校歌は次のとおりである。制定年月、作詞・作曲者名は不明である楽譜は、当時の同校教諭・籔幸子(福永)の再現によった。
一 中国連山 めぐらして 一天高く 澄むところ これぞわれらが 学び舎の 歴史ふりたる たたずまい
二 学びの窓を 彩りて 幾春秋は 過ぎゆけど 睦みつどいし 友垣の 永久のふるさと 舎人校
(注)〔校長〕①川本善太郎(明治二三年七月~)②保田堅治(同三三年一〇月~)③鈴木一三(大正二年一二月~)④谷本重徳(同九年四月~)⑤岸田虎蔵(昭和二年四月~)⑥伊藤実(同五年四月~)⑦深田吉三(同八年八月~)⑧浜辺正規(同一四年四月~)⑨山本豊信(同一七年四月~)⑩中島友太郎(同二一年四月~)⑭広富豊(同二四年~)
(注) 以上歴代の各学校長の調査では、『さくら学校誌』を参考にした。
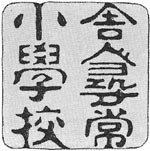 |
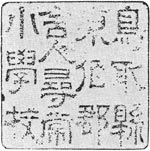 |
|
舎人尋常小学校の印影 (明治32年の同校の褒状から模写した) |
舎人尋常小学校の印影 (明治34年の修業証書から模写した) |
 |
 |
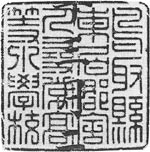 |
||
舎人小学校の最初の校旗(図案) (「舎人小沿革史」から) |
舎人尋常高等小学校の校旗 校章の制定年月、由来は明らかではない (桜小学校所蔵) |
舎人尋常高等小学校の印影 (昭和10年の卒業証書から複写した) |
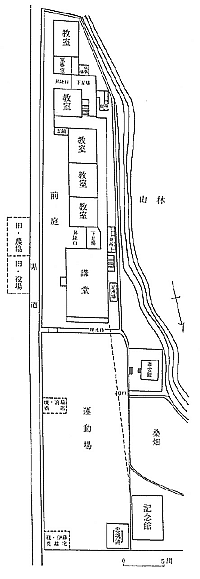 |
| 図38 昭和15年当時の舎人小学校校舎配置図 |
 |
 |
|
昭和31年当時の舎人小学校 右手前の建物が講堂(桜小学校提供) |
舎人小学校の印影 (昭和29年の卒業証書から複写した) |
舎人小学校の校歌 |
 |