第四章 近代・現代
第九節 学校教育
一 教育制度の変遷と町内の概観
(四) 昭和前期
昭暉学館の開校
昭和四年四月一日、中興寺の昭暉〈き〉山龍徳寺内に、全国でも数少ない曹洞宗の僧侶〈りょ〉を養成するための「専門僧堂」が開設された。同時に、農村青年に中等程度の学力と現代的常識を得させるための「昭暉学館」が併設された(『東郷村郷土読本』)。現在の中学校程度の教育機関である。学館長には、創始者である同寺の第三〇代住職・蒔〈まき〉田賢牛が就任した。
開校してから四年後の昭和七年、同学館が作った学生募集のチラシが残っている。それによると、教科は修身・公民・国語・漢文・国史・地理・数学のほかに、宗乗〈しゅうじょう〉(ここでは曹洞宗の学問)、余乗(曹洞宗以外の宗派の学問)を加えた九科目であった。五年制で、高等小学校の卒業者は、第三学年に入学することができた。毎日の教授時間は、学年によって午前・午後の二部とし、それぞれ三時間の半日学校であった。授業料は、一か月一円三〇銭であった。
また、昭和十三年発行の『東郷村郷土読本』には、講師として学館長のほか高橋慈航・伴乙雄・竹村秀道・前田洞禅・福井僊敬・石賀文雄の七名の名を記す。また、昭和十三年当時の生徒数は、専門部一一人、禅林部一五人であったと述べている。これは専門僧堂及び昭暉学館に学ぶ者の区分を指すものであろうが、詳細は不明である。
憎堂・学館は向学心のある青年を教育したが、太平洋戦争がぼっ発し、修行僧などが次々と軍隊に召集されたため生徒数が激減し、ついに昭和二十年三月、閉館のやむなきに至った。卒業生の数などを示す資料は残っていない。
なお、蒔田賢牛師は、仏教の奥義を究めた宗門の大御所として知られ、また、山陰を代表する漢詩人、優れた教育者でもあった。没後四〇年に当たる昭和五十九年、かつて教えを受けた弟子や卒業生が、その徳を慕って同寺の境内に顕彰碑を建立している。
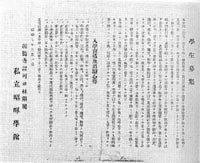 |
昭暉学館の学生募集広告 (佐美区有文書) |