第四章 近代・現代
第九節 学校教育
一 教育制度の変遷と町内の概観
(三) 大正時代
農業補習学校
前述したように、明治三十三年の改正小学校令の公布を契機に、小学校の就学率は高まったが、高等小学校などの上級校に進学する者はごくわずかであった。「東郷小沿革史」によると、明治三十七年四月当時、東郷村内尋常科卒業生の高等科への進学率は、男子四一・七パーセント、女子一六・七パーセント、全体で二五パーセントであった。大部分は、家庭で農業に従事するなど実業に携わったのである。
しかし、資本主義経済の発展により、産業教育に対する要望が次第に高まっていた。既に明治二十六年には「実業補習学校規程」が定められ、工業・商業・農業など実業に従事しようとする青少年に、その職業に必要な知識・技能を授ける機関として、実業補習学校の設置が奨励されていたのである。
県では、実業補習学校を設置する前段として、明治三十八年から攻学会の開設が指導された。町域内でも、舎人・東郷村で攻学会、あるいは夜学会開設の記録が見られる(次節「社会教育」を参照)。
大正六年、舎人尋常小学校に舎人農業補習学校が併設された。翌七年には、(注)東郷校にも補習学校の設立認可が下りている。このほか、松崎・花見両校にも設立されているが、開設年月などは明らかでない。そのいずれも、「農業」の名を冠した補習学校であった。町域内では、実業のなかでも農業が重要視されていたのであろう。補習学校の修業年限は三年であった。『青谷町誌』は、日曜日あるいは夜間の授業も認められたとする。舎人農業補習学校では、昭和二年十二月から夜間教授が開始されている。
『鳥取県教育史』によると、県内の実業補習学校と生徒の数は、大正六年度に大幅に増加している。これは県の督励によって、補習教育が青年団の重要事業に位置づけられ、半ば義務的に就学させたことによるという。青年団の組織が利用されたのである。
町内の農業補習学校については、その入学・卒業などの記録は全くないため、詳細は明らかにできない。
(注) 東郷実科専修学校の「沿革又ハ重要事項録」所収の「東郷青年学校沿革史」は、東郷農業補習学校の創設を明治三十八年十二月一日と記録する。また、東郷小学校には「東郷実業補習学校」の印影が伝わっている。いずれも詳細は不明である。
 |
 |
|
東郷農業補習学校の印影 |
昭和3年3月の松崎尋常小学校卒業写真 後方に、松崎農業補習学校、松崎青年訓練所(後述)の看板が見える。 (桜小学校提供) |
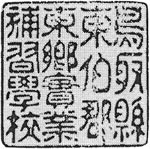 |
東郷実業補習学校の印影 |