第四章 近代・現代
第九節 学校教育
一 教育制度の変遷と町内の概観
(三) 大正時代
就学率と就学奨励
「大正三年/東郷村/松崎村/事務報告書」(方面・伊藤隆治所蔵)によると、当時の学齢児童就学率は、東郷村一松崎村のいずれも九九パーセントとなっている。明治四十一年度から尋常科の修業年限が六年に延長されたが、就学率は高率で維持されていたことがわかる。しかし、毎日の出席率となると、平均で東郷校八八パーセント、松崎校は九〇パーセントとなっている。特に、裕福でない家庭の子弟は、尋常科の高学年にもなると、家業を助けるために退学・欠席をすることが多かったようである。その防止策として、このような児童には教科書や学用品を貸し与えたり、皆勤者に一か月一五銭を扶助したりする施策がとられたという。
また、大正年間の記録である「舎人村誌巻上」によると、校長らが毎年春秋の農閑期を利用して、各部落に出向いて講話をしたり、年二回の父兄会で授業参観をさせたりして、学校教育、家庭教育の必要性を説いたという。その結果、就学率は一〇〇パーセントとなり、出席率も男女平均で九二パーセントを超えている。
なお、『奨恵社五十年史』によると、同社では大正五年から、各小学校の卒業者のうち品行方正、学業優良な児童にすずり箱などを賞与したという。
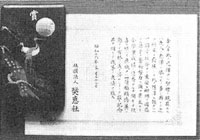 |
奨恵社の賞状とすずり箱 (川上・森田泰徳所蔵) |