第四章 近代・現代
第九節 学校教育
一 教育制度の変遷と町内の概観
(二) 明治時代
小学校令と尋常科
明治十八年に、新しく内閣制度が創設されるなど、官制の大改革が行われた。この一環として、翌十九年には、帝国大学令、師範学校令、中学校令、小学校令などが相次いで公布された。これらを一括して「学校令」と呼んでいる。我が国の教育体制を大学・中学・小学の三段階とし、小学校を初等教育機関として位置づけ、上級校への進学の道を開くなど、その後の学校教育の基本体制となった。しかし反面、こうした新しい教育政策の根本思想は、国家主義、国体主義であり、忠君愛国の精神を持つ国民の養成を目的にしていたとされる。
学校令のうち、小学校令では、義務教育を明確化した点が特徴である。すなわち、小学校を尋常・高等の二段階とし、修業年限は各四年と規定したが、父母・後見人は、尋常小学校四年を修了するまでは、児童を就学させる義務があると明記したのである。また、小学校児童の学齢は六歳から一四歳までの八年、小学校の経費は主として授業料と寄付金で賄い、もし不足する場合は、町村会の議決によって町村費から補足する、などとされた。
町域内では、明治二十年の三〜四月に各校が尋常小学校と名を変えている。
なお、高等科については後述する。
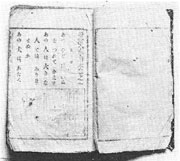 |
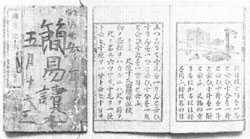 |
|
明治20年発行の『尋常小学読本』 |
簡易料の教科書(桜小学校所蔵) |