第4章 近代・現代
第8節 道路と交通
2 交通機関
人力車
『鳥取県史』によると、明治5年、境港で県内初の人力車が走り、人々は目を丸くして驚いたという。それまで、陸上で人や荷物を輸送する場合は馬、かごに頼っていた。人力車の出現は、新しい車両交通時代の幕開けであった。その後、前述した県令・山田信道の道路政策によって、明治19年6月ごろには県内の主要道路が整備された。この結果、人力車の数も急増したといわれる。
町域内に人力車が入った記録は、明治19年5月、松崎宿の足羽常蔵が福庭村(現・倉吉市)本間房蔵から1人乗り人力車1台を購入し、営業したのが初見である。しかし、その具体的な営業内容は明らかでない。また、大正9年、鉄道院が発行した『温泉案内』は、松崎駅から養生館まで人力車賃17銭、と紹介している。松崎駅が開業して以来、駅前には温泉客を運ぶ人力車が何台か待機していたものであろう。小鹿谷の坂口晃雄の談によると、電話がまだなかったころ、養生館からラッパで合図して、駅前の人力車を呼び寄せたという。
なお、『鳥取県史』によると、県内の人力車数は明治22年の2,215台を頂点にして減り始めたとしている。
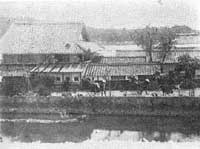 |
養生館の客を乗せた人力車 (引地・山枡直久提供) |