第4章 近代・現代
第5節 農林水産業
3 畜産・林業
牛の飼育
藩政時代から、農家では採肥用、農耕用に牛が飼養されてきた。明治3年ごろ、白石村では総戸数28戸のうち14戸が牛を飼育していたことが知られる(前掲「明治三年白石村戸籍」)。普及率50パーセントであって、他村においてもこの程度で普及していたものとみられる。下って、同18年の東郷地区における飼育状況は表67のとおりである。平均60パーセントと増加しており、この傾向は鳥取県の統計と一致する。
『鳥取県史第三巻経済篇』(以下『鳥取県史』と略称する)は、明治31・32年ごろ、牛の農家普及率がピークを迎えたとするが、町域内の状況を示す記録はない。昭和11年版『東郷村松崎村組合村勢要覧』(資料編132号)には、両村内で牛の飼育数215と記録している。当時の農家戸数は374であるから、普及率は57パーセントとなり、前表よりわずかに下降している。
「近世」の章(「松崎の馬市」の項)で述べられたように、藩政時代から松崎では牛馬市がたっていた。戦後まで松崎1区で牛市がたっていたのは、藩政時代からの慣例によるものであろう。
田畑・飛び村常蔵の談によれば、町内の「種牡牛業者」と「博労」(家畜商)は次のとおりであった。
〔種牡牛業者〕
野方の本庄嘉蔵・肇、国信の山根国吉・弥市・仲寿・門田の岡本律蔵
〔博労〕
田畑の飛村常蔵、国信の木山義雄・方地の平岡嘉市・寿千代、国信の山根芳蔵
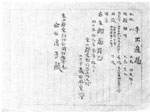 |
|
明治39年の「牛出産届」
(川上・森田正明所蔵) |
表67 東郷地区の牛の飼育状況
(明治18年)
|
村名
|
戸数
戸 |
飼育数
頭 |
普及率
% |
|
方面
|
21
|
13
|
62
|
|
高辻
|
28
|
16
|
57
|
|
川上
(麻畑を含む) |
54
|
26
|
48
|
|
久見
|
23
|
11
|
48
|
|
中興寺
|
28
|
13
|
46
|
|
別所
|
42
|
36
|
86
|
|
国信
|
27
|
18
|
67
|
|
田畑
|
38
|
19
|
50
|
|
小鹿谷
|
63
|
31
|
49
|
|
引地
|
45
|
40
|
89
|
|
計
|
369
|
223
|
60
|
(『ふるさと東郷』から)