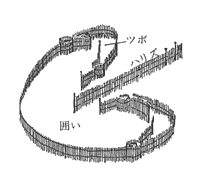第2編 歴史
第4章 近代・現代
第5節 農林水産業
2 水産業
(2)  漁業の導入 漁業の導入
 漁業のこと 漁業のこと
 〈えり〉とは、岸から直角に沖の方に竹簀〈す〉を並べ立てて、さらにその先端部を囲むように逆V字型に竹簀を設置した漁具のことである。岸に沿って回遊する魚が、ハリズという竹の障壁にぶつかって誘導され、沖の側に設けた狭いツボという部分に入り込むことから、「魚偏に入る」という国字が作られた(平凡社刊『大百科事典』)。県内では昭和18年、湖山池が琵琶湖から導入している(鳥取県刊『漁具漁法の説明』)。当時、太平洋戦争が拡大するなかで、食糧不足を補うため、鮮魚の増産、適正配給に力が注がれていたのであろう。資材の入手が比較的簡単で、魚獲能率の高い 〈えり〉とは、岸から直角に沖の方に竹簀〈す〉を並べ立てて、さらにその先端部を囲むように逆V字型に竹簀を設置した漁具のことである。岸に沿って回遊する魚が、ハリズという竹の障壁にぶつかって誘導され、沖の側に設けた狭いツボという部分に入り込むことから、「魚偏に入る」という国字が作られた(平凡社刊『大百科事典』)。県内では昭和18年、湖山池が琵琶湖から導入している(鳥取県刊『漁具漁法の説明』)。当時、太平洋戦争が拡大するなかで、食糧不足を補うため、鮮魚の増産、適正配給に力が注がれていたのであろう。資材の入手が比較的簡単で、魚獲能率の高い 漁業が着目されたものと思われる。 漁業が着目されたものと思われる。
当時の東郷湖漁業会でも 漁業に関心を示し、同18年のころから琵琶湖、湖山池を役員が視察している。同20年1月には、役員総代会で 漁業に関心を示し、同18年のころから琵琶湖、湖山池を役員が視察している。同20年1月には、役員総代会で の建設を決議した。 の建設を決議した。
以下、東郷湖漁協の記録をもとに述べる。
|