第4章 近代・現代
第5節 農林水産業
1 農業
(4) 果樹栽培
苗木の販売と栽培指導
前述した森田泰徳の研究資料(以下、「森田ノート」と略称する)によると、明治30年代後半から40年代にかけて、瀬戸兵蔵、伊藤馬蔵(注)、伊藤平蔵、長谷川秀蔵らが、二十世紀ナシをはじめ、長十郎、晩三吉、ビワ、ミカンなどの苗木を販売していたことが知られる。町域内のほか、赤碕、鳥取あるいは県外にも出荷していた。果樹栽培が普及するにつれて、苗木の需要が増加したのであろう。町域内にも、本格的に果樹の苗木を生産した先覚者があった。
『梨沿革史』によると、明治35年に創立された県立農事試験場は、果樹栽培の研究成果を普及させるため、花見村長和田など県内6カ所に指導園を設けたという。また、同34年には東伯郡農会が岡山県の果樹栽培経験者・小山益太を招いて、郡内の巡回講話を依頼している。県などによる栽培技術の指導が続けられたのである。
なお、大正元年10月、姫路市で開催された中国六県(兵庫県を含む)の生産者共進会に、金涌富吉が二十世紀ナシを出品し、一等賞(金杯)を獲得している。
(注) 伊藤馬蔵(明治3年生まれ〜昭和19年没)は、とりわけナシの苗木づくりに熱心であった。伊藤博文内閣総理大臣をもじって、「伊藤苗閣造梨〈なえかくぞうり〉大臣』とのニックネームが付けられたといわれる。栽培農家から請われると、剪〈せん〉定などの指導にも当たった(前掲『伊藤馬蔵の記録書』)。
 |
伊藤馬蔵の苗木製造等証明書 (倉吉市・石井みよの所蔵) |
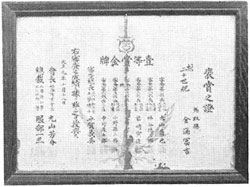 |
金涌富吉・二十世紀梨の一等賞の証 (別所・金涌盛美所蔵) |