第4章 近代・現代
第3節 戦争と災害
1 戦争と郷土
概説
天下泰平であった徳川時代も、その末期には各地で内乱が始まった。長州征伐などは、新しい時代の到来を告げる胎動であった。明治政府が誕生したあとも、(注)戊辰〈ぼしん〉戦争(明治元年)、西南戦争(同10年)などが続いた。
明治政府は、戸籍法や学制、地租改正令などを次々と発布し、新時代の体制を整えるとともに、欧米の烈強諸国に対抗しようと、富国強兵に目を向け始める。明治6年に布告された徴兵令も、その一環であった。以後、日清戦争(明治27年)、日露戦争(同37年)、シベリア出兵(大正7年)、満州事変(昭和6年)、日華事変(同12年)、太平洋戦争(同16年)と、我が国は次々と戦争への道をたどるのである。
相次ぐ戦争に、郷土からも多数の人が軍隊に召集された。名簿編3号に収録した「戦没者名簿」では、町内在籍(戸籍抹消時)の戦没者は381人を数える。召集された総人数は不明であるが、おそらく戦没者の数倍に上ると思われる。その多くは、日の丸の旗に見送られて松崎駅から出征していった(資料編106号3を参照)。
「戦没者名簿」によって、戦争ごとの戦没者の数を示した。また、太平洋戦争に限って、戦没場所ごとに人数を集計した。名簿によると、昭和20年8月6日の広島の原爆で4人が亡くなっていることが知られる。
以下、戦争と郷土のかかわりを概観したい。ここでは、町内に残る記録を重点にして述べる。太平洋戦争後、官公署においては政府の命令(進駐軍の命令ともいわれる)で、戦争遂行に関係した文書は廃棄処分したといわれる。各学校所蔵の「学校沿革史」に、墨で抹消した個所があるのは、これと軌を一にするものであろう。幸い、部落の区長宅のたんすに当時の文書が保存されている場合がある。資料編106号に採録した白石区有文書はその一例で、貴重である。
なお、各小学校に設けられた奉安殿のことなど、戦時下の学校については、「学校教育」の節で述べる。
(注)鳥羽伏見の戦いなどの総称で、明治2年に終結した。この役に、小鹿谷の遠藤常蔵(嘉永4年生まれ〜昭和8年没)が従軍したことが知られる。慶応4年の正月に、満16歳で出陣し、京都・鳥羽伏見、東京・上野、福島・原釜と転戦した。特に、明治元年8月の原釜(現・福島県相馬市)の戦いでは功を挙げ、賞を受けている。
このほか『羽合町史後編』は、戊辰戦争に従軍した農兵として藤津村・藤本清吉、長和田村・神波菊次郎、門田村・岡本次郎八、長江村・戸田茂三郎、同・羽田幸吉の名を挙げている。
| 表41 戦争ごとの戦没者数 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| (注)( )内は、戸籍抹消時の町内在籍者数である。 |
| 表42 太平洋戦争での地域別戦没者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)地域名には、その周辺の海域も含む。地域の分類方法は、戦没遺体収 揚委員会刊『大平洋戦争沈没艦船遺体調査大鑑』を参考にした。戦没者数欄 の( )は、戸籍抹消時の町内在籍者数である。 |
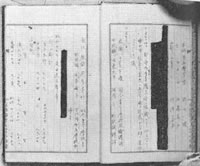 |
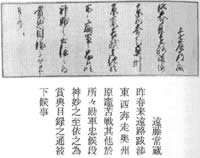 |
|
墨で抹消された東郷実科専修学校の沿革史 (町教育委員会所蔵) |
戌辰の役賞詞 (小鹿谷・遠藤辰一所蔵) |