第4章 近代・現代
第2節 財政と村政
2 主要な村政
(1) 衛生
井戸と風呂
伝染病予防など衛生改善の方策の1つに、井戸水の問題があつた。前述した「舎人村衛生組合規約」にも「井水ハ飲用雑用ヲ問ハズ総テ浚渫〈せつ〉シ破損ノケ所ハ修理ヲ加エ汚水ノ透混入等ノ虞〈おそれ〉ナカラシムベシ」と記されている。
『鳥取県史』によると、県では大正14年度から、飲料水改善のための水質検査を全県的に実施したという。当時の飲料水は井戸、河水、湧き水が利用されており、農村衛生の改善が大きな社会問題となっていた。その対策として、簡易水道の普及が考えられたが、昭和3年当時、県内の水道施設は鳥取・米子に各1、簡易水道は岩美郡津ノ井村(現・鳥取市)の1か所であった(『鳥取県史』)。
昭和13年1月に松崎小学校が編集した『郷土松崎』(松崎・立木惇三所蔵)によると、当時の松崎村内の井戸の普及状況は表38のとおりである。自家用の井戸は4戸に3戸の割で普及している。また、自家用の風呂〈ふろ〉の普及率は、12パーセントであった。多くは、近くの共同風呂を利用したのであろう。
なお、『鳥取県史』は、昭和32年の水道法の制定によって、県下に簡易水道の建設ブームが巻き起こったとする。同事業に対する県の補助は同23年から実施されていたといい、町域内でも部落単位で設置されたところがあった。高辻と方地は同27年ごろに設置されている(『町報とうごう縮刷版』)。
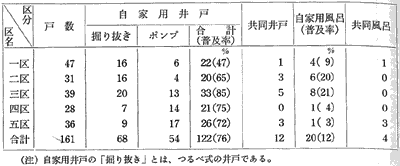
表38 昭和13年・松崎村内の井戸と風呂の普及状況