第4章 近代・現代
第2節 財政と村政
1 旧村時代の税制と財政
町村制施行前の税費目
ここでは、町村制が施行された明治22年までの各種税費目について概観する。これは、松崎地区の某家に残る税の領収証によった。
まず明治15年、北福村外6か村役場の地券税領収証が数通見られる。地券税とは、地租(国税)のことであろう。地券に基づいて、地価の100分の2.5(当時)を金納したものである。
次に、明治17・18・19年の連合戸長役場時代の領収書が見られる。主な徴税費目では、地方税のほか、村費、協議費、教育費、戸長役場費、衛生費、道路修繕費、3郡(河村・久米・八橋)連合村費などが知られる。これらの税費目では、藤津・漆原・方地・久見・中興寺・松崎・引地など、同家が土地を所有していた村ごとに賦課徴収された場合が多いが、そのいずれも当時の第4あるいは第5連合役場が領収している。
各費目のうち道路修繕費では、明治18年度・第1期分として、漆原・方地・藤津・松崎・中興寺・久見・引地の各村分、合計5円56銭八厘を納めている。これは、同年7月の暴風雨の被害に伴うものと推定される(『鳥取県史近代第二巻政治篇』)。
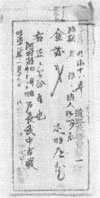 |
 |
 |
||
明治18年度の 「漆原村道路改修費領収書」 |
明治18年度の 「引地村分戸長役場衛生・ 会議費領収証」 |
明治15年の 「地券税領収証」 |