第4章 近代・現代
第2節 財政と村政
1 旧村時代の税制と財政
地券と地租
地券とは、土地の所有権を国が保証する証書である。明治5年、明治政府はいわゆる「壬申地券」を作成し、土地所有者に交付することにした。鳥取県では、同6年に地券作成のための調査を始め、同7年交付を終えている。地券には、所有者・土地の面積・所在地・地価などが記された。地価は売買価格を基準とした。しかし、壬申地券作成の際には測量は行われず、旧藩時代の土地台帳の面積を踏襲したとされている。
これよりさき、政府は既に新しい地租制度に改める準備を進め、同6年7月地租改正条例を公布した。その要点は、
1.新たに決定する地価を基準に課税する。
2.地租率は豊凶にかかわらず、全国一律に地価の100分の3とする。
3.「石代納」(米納)制度を改め、金納とする。
の3点であった。これに伴い、壬申地券に代わる新地券の作成が必要となった。新地券の地価の決め方は、5か年平均の反当たり生産額から種もみ・肥料代などを引き去って純益額を算出し、年6分の利率でその純益を生み出す額を地価とした。
新地券の作成に当たっては、土地一筆ごとの面積を実測し、平均反収を算出するなど大変な仕事であったといわれる。1年8か月を費やし、ようやく8年12月に地租台帳が完成し、仮の地券を渡す運びとなった(『鳥取県史近代第三巻経済篇』)。
なお、地租の算出率は、明治10年100分の2.5に変更された。
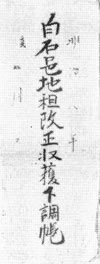 |
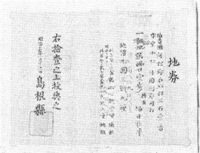 |
|
明治8年の「白石邑地租改正収穫下調帳」 (白石区有文書) |
明治8年改正の新地券 (白石・福井克之所蔵) |