第4章 近代・現代
第2節 財政と村政
1 旧村時代の税制と財政
町内の貧富等級位数表
明治26年2月、東郷村松崎村組合(議)会に提出された「貧富等級位数設定法改正按」(資料編110号)には、「地方税ノ戸数割更課及び村税賦課ノタメ」貧富等級位数を設けること、この位数は各自資産の厚薄によって査定すること、位数は3年ごとに改定することなどが定められている。しかし、何をもって1位とするか、基準は定めていない。「貧富等級位数」は前述した民等位数と同一のものと思われる。村税の内、(注)戸別割の賦課には、この位数割(民等割)と、単純に1戸何銭と徴収する平等割が併用されている(後述)。
町内には、東郷村・松崎村組合の貧富等級位数表と舎人村の民等位数表が伝えられる。時代的には明治26年から大正4年にかけてのものである。ここでは、明治時代の位数表を基に、その集計数値を表37に掲げた。このうち、最高位は、東郷村・松崎村組合は120位、舎人村は17位である。なお、表に示した東郷村・松崎村組合の位数表は、明治26年2月、組合村会に上程されたあと修正されたもので、後述する同年度予算表が依拠している総位数とは若干相違する。
各村の村税賦課に、民等位数がいつまで使われたかは明らかでない。『鳥取県史近代第二巻政治篇』は、地方税の場合、昭和15年に戸数割が廃止されたとする。また、このほか各区(部落)においても独自の民等位数が作成され、区費の徴収などに利用されていた。区によっては、太平洋戦争後までこの習慣が続いた。
(注)後述する明治時代の予算書などから、村税の戸別割には、無位の者は除かれていたと推定される。
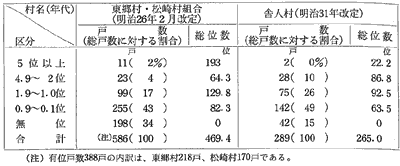 |
表37 明治時代の貧富等級状況
|
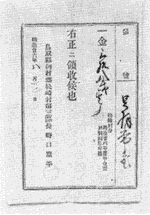 |
明治26年の「松崎3区区費(推定)領収書」 |