第4章 近代・現代
第1節 行政組織
1 行政組織の変遷
用係のこと
明治12年の数か村連合から、後の連合戸長役場の時代にかけて、役場に「用係」が置かれていたことが知られる。『鳥取県史』によると、用係とは戸長の仕事を手伝う吏員であった。前述した大・小区制時代の「手伝い」に代わるものであろう。
明治16年から翌17年5月にかけての第4連合戸長役場の用係として、伊藤善十郎(松崎宿)、森田文一郎(川上村)、神波久三郎(長和田村)の名前が知られる。いずれも、旧数か村連合時代の戸長を経験した人である。また、前掲「舎人村誌巻上」は、同17年5月以降の第4連合戸長役場(推定)の吏員として、会計主任(主任用係の意と思われる)・遠藤文平(藤津村)、庶務用係・字佐美鄭次郎(中興寺村)、租税用係・足羽準一(松崎宿)の3人を記録している。用係の選任方法は明らかでないが、以上の任用例からみて、旧・数か村連合区域で1人ずつ選任されていたのではなかろうか。文書のなかには、連合戸長の代理として用係が署名した例があり、また、数人の用係の間にも序列があったことを示すものもある。さらに、同19年ごろには、「松崎宿配置用係」の記録も見られる。
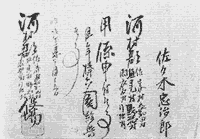 |
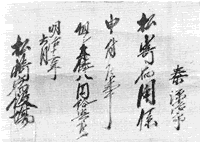 |
|
明治12年の 「長和田村外五か村役場用係任命書」 (長和田・佐々木守成所蔵) |
明治12年の「松崎宿用係任命書」 公印は「河村郡松崎宿役場印」とある。 (鳥取市・伊藤泰雄所蔵) |
|
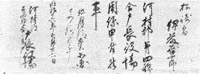 |
||
明治16年の 「第4連合戸長役場用係任命書」 (鳥取市・伊藤泰雄所蔵) |
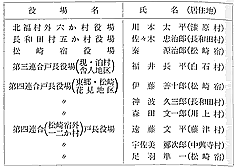 |
表32 役場用係の経験者 |