第4章 近代・現代
第1節 行政組織
1 行政組織の変遷
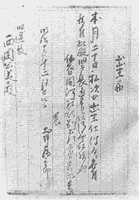 |
明治12年の出生届け (別所・西田陽二所蔵) |
明治12年1月、3新法(郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則)が施行されると同時に、大・小区制が廃止された。従来の区長に代わって郡には郡長が置かれ、町村ごと又は数か村連合で、公選による戸長が任命された。戸長の適任者がその町村にいない場合は、郡内の他町村の者を選挙することもできた。被選挙人の資格は、満20歳以上の男子で、その郡内に本籍住居を定め、地租を納める者と定められ、選挙人資格は被選挙人とほぼ同じで、その町村内に本籍住居を定める者などとされた。戸長役場は、戸長の自宅を充てることが多かったが、適当な場所を借りて設けることもあった。この時代の出生届、養子届などを資料編114号1〜4に収録した。
なお、この数か村連合の戸長の新設で、従来あった北福村、方面村など村ごとの戸長制度は廃止になったと推定される。 明治12年に編成された町域内の町村連合の様子を次に示す。松崎宿は単独で役場を持った。この編成は、同16年の連合戸長役場制度までの約7年間続いた。役場の位置は〔 〕で示した。(推定)は、当時の戸長の住所によったものである。
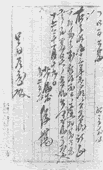 |
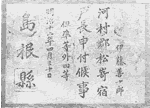 |
|
明治16年1月、北福村外六か村役場の文書 公印は「河村郡北福村 漆原村方地村 白石村 野方村 藤津村 宮内村役場印」とある |
明治12年の「松崎宿戸長任命書」松崎宿は単独であったことが知られる。 (鳥取市・伊藤泰雄所蔵) |
|
 |
 |
|
長和田村外五か村役場の印影 明治12年6月の文書によった。 |
方面村外四か村役場の印影 明治12〜14年の文書によった。 |
(注1)北福村外六か村連合……北福・漆原・方地・白石・野方・藤津・宮内〔藤津村〕
松崎宿……松崎 〔松崎宿〕
方面村外四か村連合……方面・高辻・川上・久見・中興寺 〔川上村・推定〕
別所村外三か村連合(推定)……別所・(注2)国信・田畑・小鹿谷〔不明、次項を参照〕
長和田村外五か村連合……佐美・埴見・羽衣石・長和田・野花・引地〔長和田村・推定〕
長江村外一か村連合(注3)(推定)……〔長江村・推定〕
(注1)明治十年五月二十二日、北方・福永両村が合併して、北福村が誕生した(『鳥取県史近代第一巻総説篇』)。
(注2)明治十一年十月二日、山辺・中尾両村が合併して国信村となった(『同書』)。合併に際し、新しい村名について合議した際、話し合いがつかず、両村名を組み合わせた「中山尾辺村」に決まりかけたが、中尾村の徳井文右衛門から汗入郡所子村(現・大山町)に国信村という農業優良村があるから、これにあやかっては、との動議が出て、国信村に決定したといわれる。
(注3)「花見小学校沿革史」(同校所蔵)が明治十二年五月、「音田卯三郎(注・長江村)戸長ニ任ゼラレ、本校(注・長江、門田村を校区とした長江小学校のこと)管理者タリ」と記録していることによる。同十三年六月十日付けの長江区有文書に、長江・門田両村の戸長の署名が見られ、当時両村が別個に独立していたともとれる。しかし、この文書は同十一年の入会地の紛争に関して和解したものであり、役職の署名は当時にさかのぼってしたためたものと考えられる。したがって、ここでは長江・門田で連合して役場をもったと解する。