第4章 近代・現代
第1節 行政組織
1 行政組織の変遷
大区・小区制の実施
明治6年12月、本県では前項の112区の制度を廃止して、改めて大・小区を置いた。これは、前年10月の大蔵省達に基づくものであった。県内を17の大区に区分し、その下に従来の112区を分属させ、小区とした。町域内を含む旧・河村郡は第9大区となり、112区制当時の第51区は小1区に、第53区は小3区になった。
大区ごとに区長1人、小区ごとに小区長(明治8年に副区長と改称)1人が置かれた。また、町村には戸長、副戸長が置かれた。これらは、いずれも官吏に準じた身分とされ、県が任命した。士族や、かつての大庄屋、庄屋などから登用された例が多く、しかも他地区から任命されたケースが多くみられる。給料は人民の負担とされた。また、小区ごとに、小区長の仕事を補佐する「手伝い」が1人ないし2人置かれた。小3区の場合、遠藤文平(藤津村)と神波久三郎(長和田村)の2人が任命されている(注2)(「舎人村誌巻上」野方・中村春義所蔵)。
明治6年に出された「区戸長事務章程」によると、大区ごとに会議所(後に会所と改称)を設け、大・小区長は会議所に勤める、町村の役所は戸長の自宅を用いる、と決められていた。第9大区の会議所は、小2区内の橋津村(現・羽合町)に置かれた。また、区・戸長の任務は、戸籍の編成事務を主体に、上意下達・下意上達、租税の取り立て、物産の増殖、民費の賦課などであった。特に、戸籍の編成に際しては、戸(家)に戸主を定め、戸内の総人員、姓名、年齢、続柄、職業、寺、氏神などを申告させ、家に関するすべての責任と権限を持たせた。
なお、前述したようにこの時代の区・戸長は、人民の選んだ者ではなく、上からの施策を押しつける行政官としての性格が濃かったため、町村民の不満が多かったという。そのため、県は明治8年11月、全国に先がけて町村民の意思を代表させる総代制を設けた。これは、後の町村(議)会のもとになったものである。同10年に県(島根)が出した選挙規定によると、町村の総代人は2人を定員とし、その資格は3年以上その町村に居住し、券面(地券)300円以上の不動産を持つ25歳以上の戸主などとされている(『鳥取県史』)。町内には、総代決定通知書1通が残っているほか、村惣代の氏名を記した文書が散見される(資料編113号・114号など)。
(注1)以下、本節に掲げる各種の印影は、いずれも原寸大である。
(注2)大正元年〜6年の間に、当時の舎人尋常小学校訓導・米原昇が著した郷土誌。「教育」、「政治」など12章から成る。
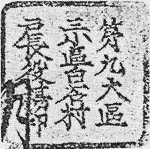 |
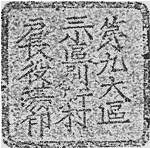 |
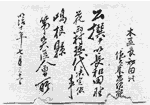 |
||
第9大区3小区白石村 戸長役場の印影 明治11年の文書によった。 |
第9大区3小区別所村 戸長役場の印影(注1) 明治11年の文書によった。 |
長和田・野花両村の 総代決定通知書 (長和田・佐々木守成所蔵) |