第4章 近代・現代
第1節 行政組織
1 行政組織の変遷
112の区制
鳥取県が設置された翌明治5年1月、県内が112の区に区分された。これは、前年に公布された戸籍法に基づく戸籍事務取り扱いに対応したものと考えられている。すなわち、同法では、地方の実情によって区画を定め、区ごとに戸長・副戸長を置き、区内の戸数・人員・生死・出入などの把握に当たらせることを定めている。
町内では、福永・北方・漆原・方地の4か村が現・泊村区域の村々とともに第51区に、残りの村はすべて第53区に属した(以下、後に掲載した表33「区制・区域の変遷」を参考にされたい)。
各区には、官選の戸長・副戸長が置かれ、戸長宅に設けられた戸籍点検所で戸籍などに関する事務をつかさどった。このため、藩政時代から引き続いて置かれた庄屋の仕事から、戸籍事務は除かれたと考えられている(『鳥取県史』)。なお、第53区には副戸長が3人置かれていたことが知られる。区制の設定と同時に郡政所は廃止された。
また、明治5年4月、本県では旧村の庄屋は、村長と呼ぶことになった。さらに、同年11月には、村長、組頭、小頭などがすべて廃止され、村長は、その任務は従来のままとして、村用役と改称した。町村の統率者の名称は、これ以後も変更が見られる(表31参照)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表31 村(町)の統率者の名称変遷
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、以下に述べる明治二十二年の町村制施行までの町村の統率者の氏名は、名簿編一号に収録した。その都度、参照されたい。
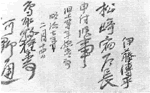 |
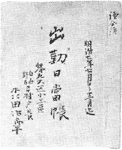 |
|
明治7年の
「松崎宿戸長任命書」 (鳥取市・伊藤泰雄所蔵) |
戸長の「出勤日当帳」
(川上・森田正明所蔵) |
|
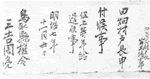 |
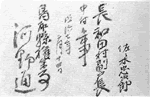 |
|
明治7年の
「田畑村戸長任命書」 岸本は小鹿谷の人である。 (小鹿谷・岸本勉所蔵) |
明治7年の 「長和田村副戸長任命書」 (長和田・佐々木守成所蔵) |