第2章 中世
第5節 中世の信仰・その他
野方の「宝垣」
「○○垣」の地名は、垣をめぐらした広い屋敷を意味するものと思われる。野方の「宝垣」もその例である。隣接する「竹ノ下」は「館ノ下」が転じたものであろう。館(たて、又はたち)は時代によりその意味が異なり、古代においては国司・郡司の舎宅、貴人・官吏の邸宅のことを指し、古代末から中世にかけては地方豪族の城砦さい〉的住宅を意味するようになったといわれる(平凡杜『大百科事典』)。いずれにしても、「宝垣」はこの地域の有力者の居館であったと思われる。
「宝垣」には白鳳時代(七世紀後半)の造立と推定される野方廃寺跡がある。この地名が当時からあったとすると、寺域を示す地名かもしれない。時代の変転により、寺が廃絶したあと、豪族の居館に変わったことも考えられる。
「九文田」は「公文田」で、荘園時代の荘官の給田、「五久」は「御給」と考えられ、同じく給田を表している。
北側にある「北田」・「北ヶ坪」は宝垣から見た命名であろう。
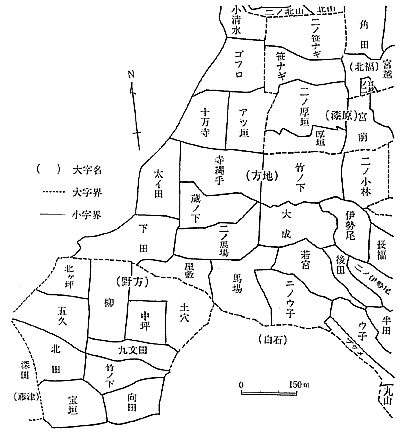
図29 東郷町野方・方地・漆原の一部地籍図