第2章 中世
第3節 室町・戦国時代
2 戦国時代の郷土
(2) 毛利氏の東伯耆支配と南条氏
戦乱の終結
元続は同13年(1585)西伯耆に侵入して河原山城(大山町、孝霊山)を攻撃したことがあったが、東伯耆においては同10年の戦いをもって戦乱は終結したとみられる。大永4年(1524)尼子氏の伯耆乱入以来、約60年間打ち続いた戦乱に田畑は戦場となり、庶民は戦火を避けて逃げまどったことと思われる。
前掲「埴見郷伝記」は、次のとおり述べている。
(前略)往昔羽柴筑前守秀吉公と毛利安芸守闘諍〈とうそう〉ニ因テ、吉川駿河守元春公橋津村駒之山ニ在城シテ、天正五年より同十三年迄兵乱ニ付、長江・門田村の放火に因って焼失致し、門田の者共は多く因州に立退、騒動の間は浪牢す。(岡本)市右衛門先祖は用か瀬へ当分住居す。後ニハ日野郡下芽〈さがりかや〉村(江府町)工流浪シ、四代前ノ市右衛門七才之年帰郷ス。法名風山宗金居士事也。長江村者共ハ会見郡ニ立退ク。音田市郎左衛門元祖同九郎右衛門は会見郡へ由緒有
このように、農民はゆかりを尋ねて流浪した様子が分かるのである。現在、日野町に音田・恩田姓が約30軒、江府町には岡本姓が10軒ばかりある。これらは長江・門田の音田・岡本家ゆかりの一族と思われる。
また、門田の前田政義家の屋号を紙屋と称するのは、同様に天正の戦乱を避けて、一時勝部谷紙屋(青谷町紙屋)に居住したことに由来するという(「聞書き」藤津・米原尊昭所蔵)。
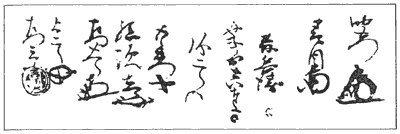
図27 中世における署名と印判の例(佐々木五郎所蔵文書から)
印判には、花押・略押・刻印が使われている。身分の低い者、
無学の者は×○のような簡単な形を描いて花押に代用した。
これを略押という(『広辞苑』)