第2章 中世
第3節 室町・戦国時代
2 戦国時代の郷土
(2) 毛利氏の東伯耆支配と南条氏
吉川氏に起請文提出
天正3年(1575)10月14日、南条元続・小鴨元清兄弟はそれそれ吉川元春・元長父子にあてて忠誠を尽くすことを誓い、亡父宗勝同様に引き立てられるよう願って血判起請文〈きしょうもん〉(誓紙ともいい、違背したら神仏の罰を受けることを神仏に誓うために作成する文書)を提出している。元続の提出したものは次のとおりてある。
今度宗勝不慮の病死、是非に及ばず候。そもそも、親に候者事、芸州(毛利氏)御威光をもって入国つかまつり、年来御引立によって、当三郎(河村・久米・八橋)違儀なく仰せ付けられ、今に御厚恩の故、安着の段、誠に御入魂〈じっこん〉浅からざる次第に候。然る間、我等の事若輩の条、近年、宗勝へ御目を懸けられる姿ニ、恐れながら相易〈かわ〉らず此節別して御心を副〈そ〉えられ、自今以後、忰家弥〈せがれいえいよいよ〉長久に相続候様ニ、毎篇御意を加えらるべきこと希〈こいねが〉うところに候。白然、他家より和讒〈わざん〉(中傷・ざん言)の族〈やから〉、子細を申乱しこれあるにおいては、尋ね究められ、礑〈はた〉と(しっかりと)救立なさるベき儀、万々忝〈かたじけな〉かるべく候。かくの如く申上候時は、芸州に対し申し、向後毛頭〈もうとう〉(少しも)別心(むほんする心)を構うべからず候、勿論ながら、元春様此度御懇切、住々〈じゅうじゅう〉(決して)いささか忘却有るまじく候。若〈もし〉右の旨趣偽るにおいては、
梵天〈ぼんてん〉・帝釈〈たいしゃく〉・四大天王すべて日本六十余州大小神祇・当国一宮大明神・大山地蔵権現・三徳山三所権現・杵築大明神殊氏八幡大菩薩麻利支尊天・天満大自在天神・神罰、冥〈めい〉罸(仏の罰)、御罰を蒙るへきもの也、仍〈よって〉誓紙件〈くだん〉の如し
天正三年 南条又四郎
拾月十四日 元続(花押)血判
元春様
元長様
参〈まいる〉
このほか南条氏の一族、重臣ら15名も同様に吉川氏に対し、元続に対する忠誠と、吉川氏の厚恩を忘却しない旨誓っている(資料編38号)。この前後に諸将から吉川氏に提出された起請文は、八通を数えるという。南条氏のほか、出雲三刀屋〈みとや〉城主の三刀屋氏、但馬守護山名氏などが、いずれも吉川元春に忠誠を誓っている。
 |
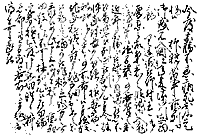 |
|
南条元続起請文(東京都・吉川重喜所蔵) |
||