第2章 中世
第3節 室町・戦国時代
2 戦国時代の郷土
(2) 毛利氏の東伯耆支配と南条氏
南条氏の羽衣石城回復
寺社領を安堵(領地を確認・保証すること)したり、新たに所領を寄進するなどの行為は、その地域を現実に支配する有力者が行うのが普通である。
この視点でみると、南条氏の羽衣石城回復は永禄5年(1562)の後半とみられる。この年の2月には倉吉市の定光寺に、5月には中山町の逢坂神杜にそれぞれ尼子義久の寄進があり、これ以後のものはない(後に興った尼子勝久のものは別個とする)。11月には代わって南条元清が野花の松尾杜に神田を寄進している(資料編4号)。この時期を尼子と南条の勢力交替期とみてよかろう。
城は回復したが、毛利氏による制約はあった。毛利氏は統治の方策上、目付役として毛利氏の直臣を領内の諸城に派遣していたようである。これを検使という。『陰徳太平記』によれば、天正8年(1580)ごろの羽衣石城の検使として、境山城守経重と小寺左衛門尉春任の名を挙げている。城主に対し、毛利氏の指令を伝えるのを役務としたのであろう。
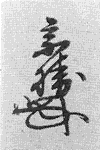
南条宗勝の花押
(山田家文書から)