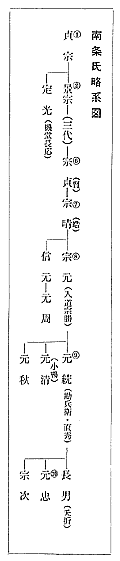第2章 中世
第3節 室町・戦国時代
1 室町時代の山名・南条氏
初・中期の南条氏
初代貞宗をはじめ、南条系図に載っている初期・中期の歴代当主のうち、7代宗皓以前に発給された古文書は、前に触れた定光寺文書は別として、まだ発見されていない。文書が伝来していないのは、度重なる戦乱で滅失したであろうし、何より大きな原因は南条氏が関ヶ原の戦いで没落し、徳川政権下の大名として郷土の地を治め得なかったためであろう。したがって、この間の郷土の歴史を史料によって述べることが難しい。『伯耆民談記』の記述も次のとおり数行で終わっている。
貞宗明徳二年に卒去して、嫡子宮内少輔景宗襲封す、この人武勇父に劣らず、景宗四代の嫡孫を、但馬守宗貞と云ふ、代々山名氏の下知を受けて家運栄へ行けり、永正十一年行令九十一歳にて卒去す、法名月法宗祐と称す、其子越前守宗(皓カ)的家督を続く、是より先き永正二年前〈さき〉の大将軍義稙〈よしたね〉卿、防州より上洛の時先鋒の衆に列し、京都に於て戦功を顕はしける、永録(正カ)十一年春秋四十六歳にて卒去し法号心証宗泉と称す、嫡子豊後守宗光(元カ)相続す、(下略)
「代々山名氏の下知〈げち〉(命令)を受けて家運が栄え」たとある。前節で述べた伯耆守護山名氏の荘園侵略の時期は、南条氏でいえば、初代から5、6代までの期間であろう。羽衣石に本拠をもった南条氏は、おそらく東郷荘を中心に所領の拡大をはかり、実力を蓄えたものと思われる。
南条系図では、南条氏の3、4、5代は実名を挙げていない。6代宗貞、7代宗皓と続き、8代宗元〈むねもと〉(入道宗勝〈そうしょう〉)に至り戦国の多難な時代を迎えるのである。