第2章 中世
第2節 鎌倉・南北朝時代
4 南条氏と羽衣石城
羽衣石城の遺構
羽衣石城の建造物も前項に類するものであったと思われる。城跡から瓦が出土しないことからみて、屋根は板葺か草葺であったことは間違いないところである。
現在見られる羽衣石城の遺構は、おおよそ次のとおりである。
解説
1 本丸=東西66メートル、南北20メートル。標高376メートル。
2・3 曲輪〈くるわ〉=曲輪とは周囲に土塁などを築き、一区画をなした区域。
4 虎口〈こぐち〉=城壁の門に枡形〈ますがた〉を造り、曲がって出入りするようにした出入り口。現在3個の巨石が残っている。
5・6 帯曲輪=本丸の下段に帯状の曲輪がある。幅5メートル〜16メートル。6は北側のみ。
7・8 曲輪=地元の人が「二の丸」、「三の丸」と呼んでいる曲輪。
9 茶の井戸=6メートル×3メートル、岩の間からしみ出た水をためたものである。
10・11・12 曲輪=尾根上に段階状に大小約一五の曲輪がある。道を攻め登る敵を側面から攻撃するための曲輪であろう。ただし、10は領主の居館跡とする説がある(後述)。
13・14 石垣=石垣状であるが、13は自然のもので、人工は加わっていないとみられる。14は使途不明である。
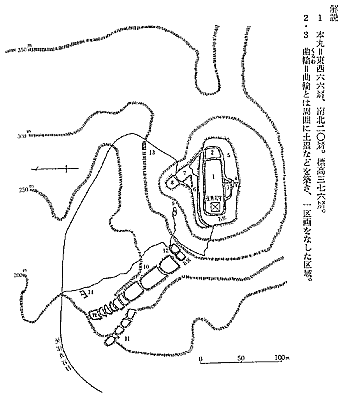
図25 羽衣石城跡概念図
(倉吉博物館・真田広幸原図)