第2章 中世
第2節 鎌倉・南北朝時代
4 南条氏と羽衣石城
貞宗以前に見える南条氏
既述のように、南条初代貞宗が3歳で父母に死別したのを、暦応4年(1341)と伝えている。しかし、そのころ既に南条氏を名乗る有力者がいたことが次の史料によって知られる。
(1) 小早川文書に、「建武3年11月24日、高師直、施行状を下し、南条又五郎に富田庄内天万郷一分地頭職(注1)を小早川道円へ沙汰付(注2)することを令す」とある(『鳥取県史』)。前述したとおり、高師直は足利尊氏の執事の職にあった。彼は尊氏の意を奉じ、建武三年(一三三六)十一月、施行状をもって南条又五郎に「伯耆国富田庄内天万郷一分地頭職」を小早川氏に沙汰付けするよう指令している。普通、施行状を受けて領国の政務にかかわるのは守護である。したがって、南条又五郎は伯耆守護の役務にあったと考えてよかろう。
(2) 小鴨氏系図中、氏基の項に、「母は南条壱岐守元伯女、元弘元年(1331)3月15日、足利尊氏卿より加冠(元服の儀式)の時、氏の字を契約(下略)」とある(富盛禅雄『小鴨氏』)。小鴨氏は前述のとおり、古代から小鴨郷を中心に勢力をもった名族である。このような小鴨氏と縁組みを結ぶことができる南条氏があったとすれば、羽衣石南条をおいて外には考えられない。
このように、貞宗の出生以前において既に南条氏を名乗る者のいたことが知られる。前項に述べた尼子氏との関係などとともに、今後解明したい事柄である。
(注1) 鎌倉時代、1荘・1郷に2人以上の地頭がいるとき、おのおのを一分地頭と呼んだ(柏書房『日本史用語辞典』による)。
(注2) 鎌倉時代、所領に関する訴訟に勝訴した方に係争地を引き渡す手続き(同書)。
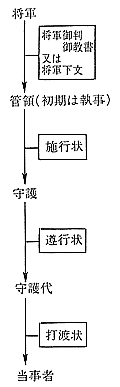
図24 将軍の命令の下達経路と文書名
(小和田哲男編『中世文書の基礎知識』から)