第2章 中世
第2節 鎌倉・南北朝時代
2 東郷氏と東郷荘
家平らの討ち死に
治承3年(1179)壷瓶<つぼかめ>山(西伯郡淀江町)で、家平・俊兼・俊家の3人が討ち死にする大事件が起こった。
『吉記』(民部卿藤原経房の日記)の寿永元年(1182)8月20日の条に次の記述がある。
伯耆国の合戦の事。風聞に云わく、伯耆国の住人成盛海六を称す。先年基保が為に滅亡せらる物なり。と基保小鴨介を称す。合戦。基保追い落とさる。死者幾千と知れず。出雲・石見・備後等国々与力す云々。
海六成盛は紀成盛のこと。紀氏は伯耆西部を代表する勢力であり、小鴨氏は小鴨郷(倉吉市)を本拠とする東伯耆の豪族であった。両者が近隣の出雲・石見・備後などの国々の兵力をも動員して激しく戦った。成盛については、「先年基保の為に滅亡せらる者なり」と割注して、寿永元年以前にも合戦があったことを示唆している。この合戦が、家平の項に記された治承三年の戦いではなかろうか。
源平両氏の争乱において、各地の在地領主は次第に源氏・平氏の兵力に組み入れられていった。『鳥取県史2中世』(以下この章では『鳥取県史』と略称する)によれば、当時小鴨基保は平氏に与同(味方になること)していたというから、これと戦った紀氏・東郷民は源氏方とみられる。
俊平を葬った「金人庄」は「舎人庄」の誤りであろうが、舎人地区には「堀内」の地名は残っていない。「堀内」を「方地」に比定する説があるが、少し無理であろう。「堀」のつく地名は、漆原に字「堀田」がある。
また、家平の墓がある「東郷内和田」は従来「長和田」に比定されていたが、ここでは「庄」の脱字とみて「東郷庄内、和田」と解したい。「東郷庄内」という表現はこの系図に例があり、「和田」の地名は田畑<たばたけ>の東郷川右岸の高辻寄りにある。和田には五輪塔が現存している。ほとんど壊れて完全なものはないが、空風輪だけは4、5個確認できる。
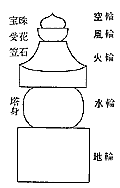 |
 |
|
図23 五輪各部の名称 (山川出版社『歴史散歩辞典』) |
和田の五輪塔 |