第2章 中世
第2節 鎌倉・南北朝時代
1 東郷荘
絵図の裏書
この絵図には次のような裏書がある。
伯耆国河村郡東郷庄絵図なり
領家・地頭和与中分の間、是より道路有るの所は、その道を以て堺となし、堺無きの所は、その際目〈きわめ〉に朱を引き畢〈おわ〉んぬ、朱の跡は、両方寄合いて堀通しめ畢んぬ、此の如くして、東西両方に中分既に畢んぬ、ただし、田畠を等分の間、伯井田は西方たりといえども、此の田の内を以て、なお東方に割〈さ〉き分つ所なり、是故に、馬野ならびに橋津及び伯井田等は、東西に相交わる所なり、小垣に至りては、北条河の東西ともに以て東分なり、此の絵図に東分・西分とおのおのその銘を書く所なり、そもそも南方の堺に当りて、置福寺.木谷寺此の両方の中間に朱を引きて堀通し畢んぬ・而して件〈くだん〉の堀の末、深山たるに依って、峯あり谷あるの間、堀通す能わず、然れば、その際目の朱より三朝郷の堺に至るまでは、ただ朱の通り端直〈すぐ〉に見通して、東西の分領を存知せしむべきの状、件の如し
正嘉弐年(一二五八)十一月 日
沙弥
散位政久(花押)
正嘉弐年ニ東西南中分の絵図なり、
正嘉弐年カラ貞和二年迄〈マデ〉、八拾八年歟〈か〉
右正嘉ノ年号ヨリ元和六年まで、三百六十三年歟
(注)「寂」の異体文字
領家とは松尾社を指すが、地頭の氏名は確定できない。
和与とは、荘園の支配権をめぐる領主・地頭間の争いなどで、提起した訴訟を取り下げて和解することをいい、和与による下地中分を和与中分という。東郷荘の場合は、和与中分の方法によったのである。
終わりに記名した二名は、沙弥〈しゃみ〉
また、末尾に追記してある文言は、おそらく貞和2年(1346)と元和6年(1620)に、この絵図を紛争の解決、あるいは社領安堵のための証拠として使ったことを示す記録であろう。
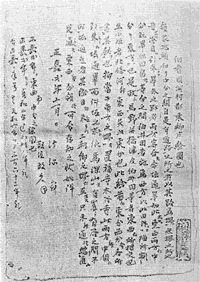
東郷荘絵図の裏書