第1章 原始・古代
第5節 奈良・平安時代
3 仏教文化の開花
久見古瓦出土地
東郷中学校の南側に隣接した果樹園から、かつて大量の瓦が出土し、久見のこの一帯は、野方・弥陀ヶ平廃寺の瓦を焼いた窯跡と考えられていた。しかし、同校の敷地内から出土した円形に近い平らな面を持つ2個の石が、昭和50年に礎石であると確認されたことから、寺跡あるいは群衙跡の可能性が強まってきた。
東郷中学校のある辺りは、字「向畑」である。条里制の項で述べたように、方格地割が整然と並んだ久見の一帯に続いて位置している。字「向畑」は、北の辺の長さが南に比べて少し短い台形状であるが、南北125メートル、東西の平均値は約116メートルと推計できる。恐らく、この区画内に建物の遺構が残っていると思われるが、今のところ前述の礎石のほかは見つかっていない。
後述するが、久見出土の瓦の最古のものは7世紀後半と推定されている。したがって、そのころまでには建てられた建物であることが分かる。しかし、7世紀中期には、既に建てられていた野方・弥陀ヶ平廃寺と余りに距離的に近い(直線で約1.6キロメートル)ことから、寺ではなく郡衙の可能性も強まっている。伯耆国庁は近年の調査で、遅くとも8世紀中ごろには建てられていたと推定されている。律令制が確立する過渡期にあって、国庁より郡衙の方が早く整備されたといわれ、7世紀の後半に久見に郡衙が建てられたとしても不思議ではない。
なお、久見では8世紀後半の瓦も見られるが、8世紀前半の瓦が全く見られない。7世紀後半に建てられてから、約100年間、瓦の葺(ふ)き替えがなかったものか。仮に久見を郡衙跡とすると、あるいはこの1世紀の間に、郡衙がよそに移転したことも考えられる。
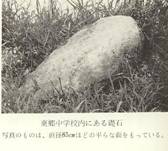 |