第1章 原始・古代
第4節 古墳時代
3 郷土の主な古墳と遺跡
門田・片平古墳群
大平山の東側の山すそに位置する門田字「片平」を中心とする一帯は、37基の古墳が点在し、片平古墳群と呼ばれている。このうち、内部主体が判明しているのは横穴式石室23基、箱式石棺3基である。付近に玄室は、4周に平石を横長に立てて構成されていた。天井石は失われていたが、4周の一部は、さらに平石を小口積みにして持ち送りにしている状態で見つかった。羨道は玄室より40センチメートルも高く、玄門の両脇に薄い板石の袖石を設け、さらにその外側中央に同様の板石を立てて入口を閉鎖していた。また、羨道部の側壁は、一方は石を立て、一方は小口積みにするという変則的な造りであった。玄室内で時代の異なる三形式の須恵器が出土したことから、少なくとも3回の埋葬が行われたと考えられている(『倉吉市史』)。
5号墳(門田字「小五郎」)は、以前から封土の大部分が流失し、主体部の横穴式石室が露出していた。発掘調査は昭和52年に実施された。
この結果、玄室内などから勾玉1、金環1、ガラス玉50、鉄斧1、鉄鏃3、打製石斧1のほか、土師器や須恵器の土器(坏・蓋・壼など)が出土した。こうした遺物以上に、同古墳を特色づけたのは、石室の築造方法や墳丘のすそを巡る列石が確認された点である。
石室の天井石や玄門の板石は既に失われていたが、残っている石組みなどの状態(写真前掲)から、その築造方法が明らかになった。まず玄室を構成する3枚の大きな板石は、あらかじめコの字形に掘った穴に沿って、1.奥壁、2.北西壁、3.南東壁の順に立てた。その際、土や根石を使って、根元を固めながら、互いにもたせかけないよう、独立させて立てたと思われる。これらはいずれも安山岩である。羨道の両壁にはそれぞれ一枚石(高さ1.2ートル)を用い、根元を掘らないで、一部を玄室の側壁にもたせかけて立てている。また、玄門となる左右の板石は、根元の穴に固定させながら、玄室の両壁に対して直角に立てていたものと想像される。
こうして横穴式石室を構築し、封土をある程度積み上げたあと、天井石を載せ、さらに封土を積み重ねながら築き上げたものと思われる。なお、玄室の床面は、底に黄褐色の土を入れて突き固めたあと、20センチメートル×30センチメートルほどの板石を、玄門に接する部分から奥壁に向かって、少しずつ重ねるように敷いていたと思われる。その大部分は抜き取られていたが、五枚が残っていた。
玄室は、長さ1.5メートル、幅1.6メートル、高さ2.2メートル、羨道は長さ1.4メートル、幅1.7メートルあった。
墳丘のすその列石は、底部から20センチメートルほど高い部分にあり、羨道の入り口から墳丘全体の3分の1ほどにかけて、大小の自然石10数個を巡らせているのが見つかった。こうした墳丘のすそに列石を巡らせる例は、東伯耆にはなく、北九州に見られるといわれる。
出土した遺物のうち、玄室内の須恵器の蓋〈ふた〉坏は、ほとんど完全な形であった。7世紀前半のものとみられることから、古墳の築造時期が推定できる。また、羨道部の前方、前庭部には一面に須恵器の破片が散乱していた。この付近で墓前祭が行われたあと、捨てられたものとみられている。そのうち、須恵器の無頸壺は、この地方で類例を見ない珍しいものという(東郷町教育委員会『片平5号墳発掘調査報告書』)。
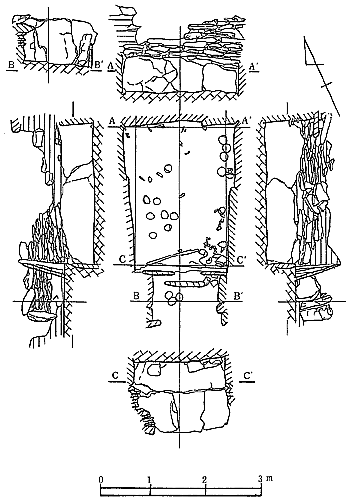
図8 片平4号墳石室実測図(『倉吉市史』による)
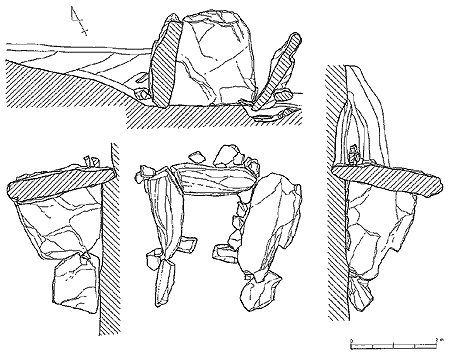
図9 片平5号墳石室実測図
(『片平5号墳発掘調査報告書』による。土質の種類は省略した)