第1章 原始・古代
第4節 古墳時代
3 郷土の主な古墳と遺跡
佐美の住居跡
昭和54年に、佐美古墳群のうち、4号墳(埴見字「佐美谷」)の発掘調査が行われた。その結果、同四号墳は5世紀中ごろのものと思われる小円墳であった。また、4号墳と一部重複した形で、新たに小形の箱式石棺をもつ小円墳(13号墳・写真前掲)が発見された。付近からは、土師器の高坏・壼、砥石なども出土している。しかし、この調査では、現在の佐美谷水田より比高約25メートルの丘陵先端部に、古墳時代の住居跡が発見されたことで注目を集めた。同時代の町内の住居跡としては、土師器などが出土した宮内・第4遺跡、藤津・大鼻遺跡、長江遺跡が知られていた程度で、発掘調査でのはっきりとした遺構の確認は初めての例であった。
そうした意味で、ここでは住居跡を取り上げて述べる。住居跡は竪穴式一基であった。その平面は、各コーナーが弧〈こ〉形を描き、全体に円形に近い隅丸方形を示していた。床面は3.5メートル×4メートルの広さで、約50センチメートル掘り下げてあった。柱穴は、中央に1個と、それを取り囲む4個がみとめられた。中央の柱穴は二段掘りになっていて、直径55〜70センチメートル、深さ10センチメートルの掘り込みの中央部を、さらに直径45センチメートル、深さ37センチメートル掘り下げてあった。4個の柱穴は、2.2〜2.3メートルの間隔で、それぞれ直径30〜50センチメートル、深さ40〜50センチメートルあった。床面から砥石1個、埋め土の中から4世紀前半のものと推定される土師器の細片が見つかっている。
このほか、住居跡に接してその西側に、直径85センチメートル、深さ1メートルばかりの大きな土墳が見つかった。住居跡に関連したものであろうが、用途など詳細は不明である。
この住居跡は、4号墳との切り合い面の関係などから、古墳の築造に先行するものと判明した。もとの住居跡に古墳が築かれたものである。恐らく、4号墳や13号墳の造営で壊された住居跡が幾つかあったであろう。古墳群の形成以前に、小規模ながら、1つの集落が営まれていたことは確実とされている(東郷町教育委員会『佐美4・13号墳発掘調査報告書』)。

佐美の住居跡(矢印、水田から比高25mの高地である)
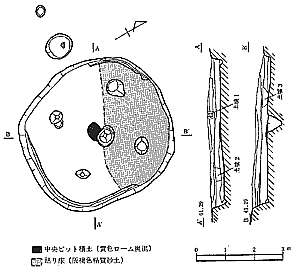
図7 佐美4号墳墳頂部の住居跡図
(『佐美4・13号墳発掘調査報告書』による。断面図の土質の種類は省略した)