第1章 原始・古代
第4節 古墳時代
3 郷土の主な古墳と遺跡
野花・北山1号墳
昭和55年に国の史跡に指定された、山陰地方で最大の規模を誇る前方後円墳・野花の北山1号墳は、東郷湖の南側、野花字「北山」の小高い丘陵(標高約50メートル)の尾根を利用して築かれている(口絵の写真を参照)。湖を挟んで、ちょうど馬ノ山古墳群と相対する位置にある。北山1号墳をはじめ、前述した馬ノ山4号墳、宮内・狐塚古墳の大型前方後円墳は、いずれも東郷湖を見下ろす景勝の地に築かれている。自然の地形を利用した結果とはいえ、こうした展望の良い場所が選ばれていることは、被葬者の死後の魂を慰める意味があったのかもしれない。
北山1号墳はほぽ原形を保っており、全長110メートル、後円部の直径70メートル、高さ12メートル、西南西を向く前方部は長さ56メートル、幅は先端で62メートル、くびれ部で43メートル、高さは11メートルである。前方部の幅・高さの規模が、後円部に匹敵するぐらいよく発達しており、中期古墳の典型的な特徴を示している。
発掘調査は昭和41年3月から、米子市の山陰考古学研究所を中心として実施された。調査区域は後円部の墳丘部分である。この部分は大正年間に盗掘されていた(第1主体)が、発掘調査で新たに箱式石棺(第2主体)が発見された。これは盗掘を免れていた。
第1主体は、表土下2.5メートルにあったとみられ、規模は長さ5〜6メートル、幅と高さ1メートル内外と推定された。5〜6枚の蓋〈ふた〉石を用い、側壁はへぎ石を積み重ねた堅穴式石室であったとみられている。石室の周辺は、長さ6.2メートル、幅4.3メートルにわたって角礫〈かくれき〉が敷き詰められ、その西寄りには長さ12メートル、幅0.3メートルの、へぎ石(輝石安山岩)片で覆った排水溝が設けられていた。
第2主体の箱式石棺は、第1主体の南側にあり、長さ1.6メートル、幅0.5メートル、深さ0.4メートルで、底にはへぎ石片が敷かれていた。蓋石、両側の壁とも2枚の板右、で組まれ、石棺の内面は一面に朱が塗られていた。石棺の中からは人骨片のほか、勾玉〈まがたま〉・管玉〈くだたま〉・刀・銅鏡(龍虎〈りゅうこ〉鏡・後述)などの副葬品が出土した。蓋石の位置は、表土下1メートルであった。このほか、後円部の頂上から中腹にかけて並べられていたと思われる円筒埴輸の破片や、葺石〈ふきいし〉と思われる河原石・角石、また武具・鶏などの形象埴輸の破片、丹〈に〉塗りされたうえ、竹ざるの圧痕が付けられたざる形土師器3個分(うち1個は完形品)など、が発見されている。
北山1号墳は、宮内の狐塚古墳に少し遅れて、5世紀前半の築造と推定されている。山陰地方で最大の規模を持つほか、出土した形象埴輸が豊富なことなどから、第1級の古墳とされている。
なお、同1号墳の後円部から50メートルほど東側に、27号墳と呼ばれる円墳がある。直径22メートル、高さ2.8メートルの中型であるが、変型四神四獣鏡(後述)が出土したことで知られている(山陰考古学研究所『山陰の前期古墳文化の研究1』)。
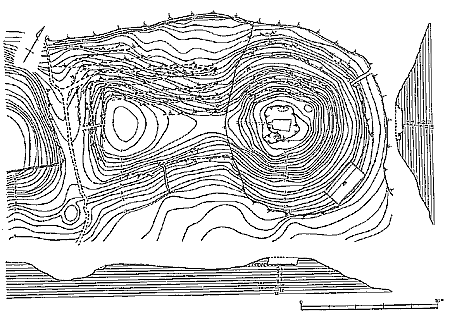
図5 北山1号墳の墳丘実測図
(『山陰の前期古墳文化の研究I』による)

北山1号墳発掘現場の全景
(手前が第1主体、奥が第2主体)
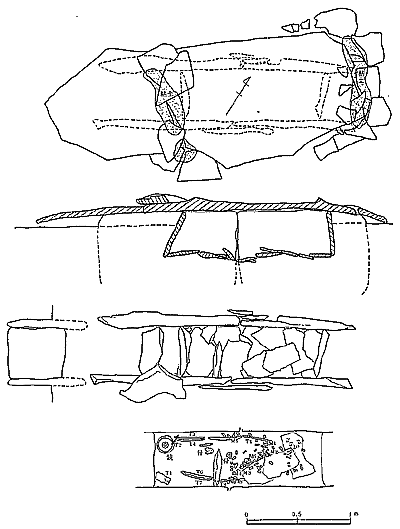
図6 北山1号墳第2主体の実測図
(『山陰の前期古墳文化の研究I』による。Tは鉄器、Mは勾玉を示す)