第1章 原始・古代
第4節 古墳時代
3 郷土の主な古墳と遺跡
宮内・狐塚古墳
東郷湖の北東部に、かなり険しい丘陵地が突き出ている。その一角、湖に面した宮内字、「狐〈きつね〉塚」に、尾根の先端を利用して大型の前方後円墳が造られている。これが、宮内・狐塚古墳と呼ばれるものである。
全長は、現在では90メートル、復元すれば95メートルはあったと思われる。後円部は直径55メートル、高さ9メートル、前方部は西南西を向き、長さ40メートル、幅は先端部で43メートル、くびれ部で20メートル、高さは7.5メートルあったと計測されている。前方部が長いうえ、しかも幅・高さとも後円部に比べて小さく、古い型の特徴を示している。
発掘調査は実施されていないが、埋葬施設は堅穴式石室であろうと推定されている。また付近では、古墳の周囲に巡らしてあったと見られる大型の円筒埴輪の破片や、葺石〈ふきいし〉が出土している。これらの出土品や古墳の形、また立地条件などから、狐塚古墳は馬ノ山4号墳より遅く、後述する北山1号墳にやや先行する、古墳時代中期(5世紀前半)の築造と推定されている(山陰考古学研究所『山陰の前期古墳文化の研究Ⅰ』)。

宮内狐塚古墳(左側手前)
矢印は野花の北山1号墳(後述)
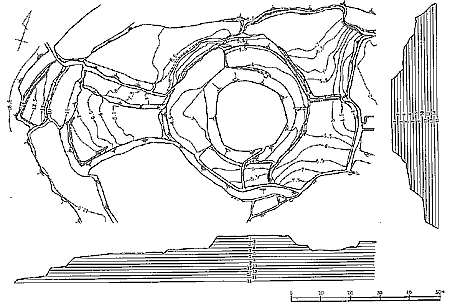
図4 宮内・狐塚古墳の墳丘実測図
(『山陰の前期古墳文化の研究I』による)