第1章 宗教法人
第3節 寺院
9 長江山永福寺
о所在地 東郷町長江867
о宗 旨 禅曹洞宗通幻派
о本 尊 薬師如来
о住 職 森田文輝
現在地に移ったのを天正元年(1573)、祖律の代とすると、祖律は元禄7年(1694)に死去しているので、その間だけでも120年を超えることになる。疑わしい点もあるが、一応寺記に従っておく。
こうして当寺は、龍徳寺4代・祐仙を開基とし、祖律は鑑住(注)となる。鑑住時代は3代で終わり、明和3年(1766)、千丈を迎えて2世とした。
寺記には「由緒書等茂有之候得共、都而(すべて)本寺江相納居候処、本寺一八世悟白長老代火災之節、古書類等一切焼失」したとあり、本寺である龍徳寺と共に、当寺の由緒書きなどもすべて焼失したと記録する。
本堂は元文3年(1738)、田後の惣(そう)次郎を棟梁(りょう)として改築され、同年本尊薬師如来の開眼をしたと伝えられる。また現在、本堂正面に掲げられている「長広山」と彫った扁(へん)額も同じ年のものであるという。
明治33年11月25日、開山堂を新築し、昭和22年8月22日に再建した。また同56年8月10日、森田英之の寄進によって、庫裏を増築(25坪)した。
当寺には経巻を納めた箱があり、「為乾室利貞信女菩提也。宝永五戊子(つちのえね)七月吉祥日。長江村長広山永福寺」と記載されている。これは、宝永5年(1708)7月、乾室利貞信女(かんしつりていしんにょ)の菩提を弔うために寄進されたものである。
弁財天一五童子を中心にした像である。空海が天長7年(830)7月7日、相州江之(えの)島で行った秘密護摩修法の際に作られた像と伝えられる。
о本堂本尊前卓
寛政7年(1795)2月13日に完成したものである。大工は門田の前田徳右衛門。材料はケヤキで、彫刻はまれに見る優美さである。
о法衣
5世・大忍の時代、寛政9年(1797)に音田所兵衛が寄進した赤地錦の法衣で、大切に保存されている。
о観音・地蔵堂
昭和60年6月30日に「観音・地蔵堂」が完成した。長江出身の山根勝太郎・恵美子夫妻(大阪市生野区在住)と長男貞一が寄進したものである。また、その天井絵は、倉吉市の洋画家・福留章太、天女絵額2枚は小島円宗画伯(大阪市)の筆によるものである。
о永福寺の鐘
同寺の鐘については、享保12年(1727)2月に作られ、その後、安永3年(1774)4月に作り直されたとする記録がある。前者は音田茂右衛門が施(せ)主となっている。後者は音田夫兵衛が初声施主で、その鐘銘中に「従来からの鐘は、小さく、そのうえ壊れていて、音響も悪い」との意が記してある。
о観世音札所
旧河村郡には33か所の観世音の札所があった。町内には羽衣石堂(16=札所番号、以下同じ)・花見堂(17)・長和田長伝寺(18)・九品山大伝寺(19)・桂男(かつらお)寺(20)・田畑堂(21)・松崎龍徳寺(22)・藤津堂(23)・方地堂(24)・漆原万福寺(25)・福永堂(26)・長江堂(29)の12か所があった。
 |
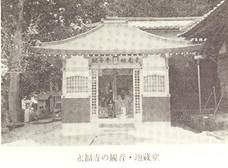 |
 |