第4章 近代・現代
第3節 戦争と災害
3 自然災害
明治時代の水害
「白石区有文書」によると、明治4年5月と6年8月に、同所で洪水に伴う被害が出たことが知られる(資料編105号)。橋や堤防などが破損したため、当時の大庄屋あるいは県参事(後の知事)に、援助を願い出ている。
続いて同26年10月、県内を襲った大暴風雨は町域内にも大きな被害をもたらした。『鳥取県史近代第二巻政治篇』は、県内の被害状況として死者219人、行方不明109人、流壊家屋4,698戸などと記録している。季節的にみて、台風であったと思われる。
東郷湖周辺の状況については、「大字門田村水災景況取調書」(門田・岡本稚樹所蔵)や『羽合町史後編』が記録している。これらを総合すると、同月11日から3昼夜降り続いた雨が4日目からは暴風雨となり、天神川の堤防が各地で決壊し、あふれ出た水が羽合平野を経て、東郷湖に流入した。このため、湖面は平時より最大で15尺有余(約4.5メートル)も上昇した。町域内の各河川の堤防は決壊し、道路や田畑の冠水、家屋の流失・浸水、山崩れなどが相次いだ。門田の場合、村道の破損5か所、山崩れ100余か所、用水路の破損7か所、家屋の転倒流失2戸、浸水家屋60余戸、橋の流失1か所などの被害を受けた。前掲の岡本家文書は、14日夜の大洪水について「風雨ノ為メ一灯ヲ点ズル能ワズ、救命ヲ呼ブ声暴風雨ニ和シ、其ノ惨状一々詳記スル能ハザルナリ」と記している。
また、『(注)東郷村郷土読本』所収の「水災記」は、川上・麻畑間の道路が流失したほか、東郷湖周辺の10か村以上で人家に浸水した、引地の養生館は屋根の棟が少し見える程度であった、などと記している。
このほか、藤津の中嶋俊男家では、裏山が崩れて家屋が倒壊し、家族のうち男2人、女3人が死亡したと伝承する。『羽合町史後編』によると、死者は舎人村で16人、東郷・松崎両村で8人であった。
(注)昭和13年10月、東郷尋常高等小学校郷土室が編さんした郷土誌。自然地理のほか、同校の沿革、二十世紀ナシの栽培史、東郷温泉史、年中行事、民話・伝説などが記された貴重な資料である。
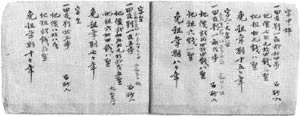 |
||
昭和26年「水害荒地免租年期写」の一部
免租期間8か年、10か年、15か年などと被害が 甚大であったことを物語っている。 (佐美・竹内英俊所蔵) |
||
 |
 |
|
「東郷村郷土読本」の表紙 |
明治26年の水害被災者救援に対する感謝状 (白石・福井克之所蔵) |
|