第1章 原始・古代
第5節 奈良・平安時代
4 伯耆一ノ宮と経塚
銅経筒の銘文
伯耆一ノ宮の経塚から発見された銅経筒には、次の銘文が刻まれている。
釈迦大師壬申歳入寂日本年代記康和五年癸未歳粗衣文籍勘計年序二千五十二載也今年十月三日己酉山陰道伯耆国河村東郷御座一宮大明神御前僧京尊奉供養如法経一部八巻即社辰巳岳上所奉埋納也願以此書写供養之功結縁親疎見聞群類縦使雖異受生之所昇沈必定値遇慈尊之出世奉堀顕此経巻自他共開仏之知見仍記此而已願以此功徳普及於一切我等与衆生皆共成仏道釈迦舎那成道場成正覚一切法界中転无上輪
正遍知者大覚□(位ヵ) 辺際智満方知断
補処今居都率天 下生当坐竜花樹
願我生生見諸仏 世世恒聞法華経
恒修不退菩薩行 自他法界証菩提
〔読み下し文〕
釈迦(しゃか)大師壬申(みずのえさる)の歳(とし)入寂(じゃく)。日本年代記康和五年癸未(みずのとひつじ)の歳は粗(あらあら)文籍に依(よ)って年序を勘計すれば、二千五十二載也(なり)。今年十月三日己酉(つちのととり)、山陰道伯耆国河村東郷に御座(いま)す一宮大明神の御前(注)で僧京尊は如(にょ)法経一部八巻を供養し奉り、即(すなわ)ち社の辰巳(たつみ)の岳上に埋納し奉る所也。願わくは此(こ)の書写供養の功を以(もっ)て、結縁(けちえん)の親疎、見聞の群類が縦使(たとい)生を受くるの所を異にし、昇沈必定と雖(いえど)も、慈尊の出世に値遇すれば、此の経巻を堀り顕(あら)わし奉りて、自他共に仏の知見を開かんことを。仍(よ)って此(ここ)に記す而已(のみ)。願わくは此の功徳(くどく)を以て普(あまね)く一切に及ぼし、我等と衆生と皆共に仏道を成し、釈迦舎那(しゃな)道場を成し、正覚(しょうがく)を成し、一切法界中於无(む)上輪を転ぜんことを。
正遍知(しょうへんち)者は大覚(だいがく)□辺際智(へんさいち)満ちて方(まさ)に知断えんとす、補処(ふしょ)は今都率天(とそってん)に居すも、下生(げしょう)すれば当(まさ)に竜花樹(りゅうげじゅ)に坐すべし、願わくは我生生(しょうじょう)して諸仏に見(まみ)え、世世恒(せぜつね)に法華経を聞き、恒に不退菩薩(ぼさつ)行を修し、自他法界菩提(ぼたい)を証せんことを。
(倉吉古文書を読む会編『鳥取県中部の古文書』による)
銘文は、「今年康和五年は釈迦が亡くなってから二〇五二年に当たり、末法の時代に入った。そのため、伯耆国河村東郷に鎮座する一ノ宮大明神の御前で、僧京尊が如法経(法華経)一部八巻を供養し、社殿東南の丘の上に埋めておく。この経文書写の功によって、すべての人が弥勒菩薩の出現に出合えば、この経巻を掘り出し、自他ともに仏の悟りを開くことを願う。
釈迦は悟りを聞いて、仏法世界の最上の地位にあるが、やがて弥勒菩薩として、この世に姿を現されるであろう。私は、生きかわり死にかわり、いつの世までも諸仏にまみえ、常に法華経を聞き、修行を重ねて、すべての人が悟りを開くことを願う」との意である。
(注)「一宮大明神の御前で僧京尊」は、「一宮大明神御前僧、京尊」と読む説もある。
また、鳥取県教育委員会編『鳥取県文化財調査報告書第一集』は「一ノ宮経塚において如法経供養の行われた康和五年一〇月三日は一ノ宮神宮寺と本末関係にある筈の叡山坂本の日枝神社神宮寺の塔の落慶式と同日であることは、まことに奇縁というべきであるが、その因縁はまだ不明である」としている。
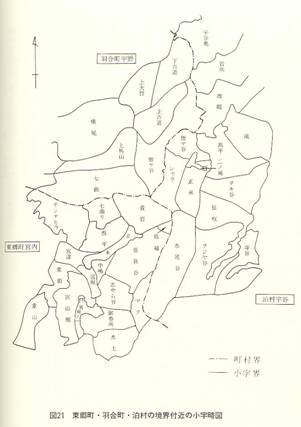 |