第2編 歴史
第3章 近世
第4節 庶民の生活
6 温泉・東郷池の利用
「東郷池面鏡」の所伝
「東郷池面鏡(とうごうちめんのかがみ)」と題する写本が伝わっている。筆者は「松崎中町、市橋栄寿軒月人」という人で、著作時期は天保年間(1830〜43)と推定される。
内容は北条の茶臼山城主俣野(またの)五郎影久と亀形(きぎょう)か城(松崎城)主川毛伯耆守家成との合戦の物語が主である。俣野五郎に攻められて亀形か城がまさに落城にひんしたとき、城が城地の丘陖もろとも池中に動(ゆる)ぎ出し、寄手の大軍が池で溺(でき)死するなど興味本位の読み物である。
ただ、この中の一部に温泉に関する記事がある。引用すれば、「その所(蜀漆(くさぎ)地蔵、中興寺)より寅(とら)の方(ほぼ東北)に当りて、中興寺といへる在所に温泉湧(わ)き出で、諸人病苦を退癒(たいゆ)させしめぬれば、近郷近郡は申すに及ばず、近国より人々入湯に参りければ(中略)、俣野の郎等久留目才蔵という者、農家に入りて黄牛(あめうじ)(あめ色で上等な牛)1疋(ぴき)引出し来りて、この温泉に切って落とし入れけり。この后(のち)涌湯ぬけて、東郷の池中に涌き出ずるとなり。この事後代に残りて、湖中の湧湯を見聞して悋(惜)(お)しまぬ人はなかりけり」と述べている。
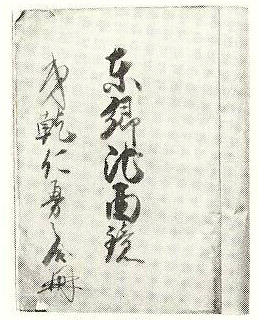 「東郷池面鏡」表紙 |