第2編 歴史
第3章 近世
第2節 鳥取池田家の成立
1 在方制度
制札場
藩政時代には、藩の法令などを農民・町人に周知するため、領内所々に制札場を設けて、法令を掲出した。寛永9年(1632)には、領内26か所に設けられ、うち河村郡では、泊・松崎の2か所であった。のち増設されて、湊村(のちの橋津)・長瀬・穴鴨が加わり5か所となった。
制札場が松崎のどの辺りに置かれたか明らかではないが、明治18年、松崎宿外12ヶ村戸長武中吉蔵が編集して、鳥取県令山田信道に進達した「伯耆国河村郡松崎宿誌」(鳥取県立図書館所蔵)には、次の記事がある。
四、里程
鳥取県庁より西方9里26町、所轄郡役所(倉吉)より東北2里22町30間、泊宿へ2里5間、但本宿字仲町掲示場を以て元標となす。
掲示場の前身を制札場と考えると、制札場は仲町(松崎3区)にあったとみられる。
松崎の町年寄が役中諸事を筆録した「御用日記」の安政4年(1857)2月の項に「御制札場屋根大破に及び候に付、御修覆願い上げ奉り候」との記事があり、制札場は屋根付きであったことが知られる。
次に制札の文言(もんごん)を例示する。
1、諸国在々所々におゐて新銭鋳候事、堅く停止也。若し相隠し鋳出す輩あらバ、申出すべし。仮令(たとえ)同類たりと云とも、其料(とが)をゆるし、御褒美下さるべし。自然脇より訴人これあるにおいては、本人は申に及ばず、5人組同罪に行ふべし。 びに其所の者迄も曲事(くせごと)(法にそむくこと)たるべきものなり
寛永18年(1641)2月3日
1、切支丹宗門ハ累年御制禁たり。自然不審成者これあらバ申出すべし。御褒美として
ばてれん(司祭)の訴人銀5百枚
いるまん(宣教師)の訴人同3百枚
立帰り者の訴人右同断
同宿 びに宗門の訴人銀百枚
右の通りこれあるべし。たとひ同宿宗門の内たりといふとも、訴人に出る品に寄、銀5百枚下さるべし。隠し置、他所より届に於てハ其所の名主 びに5人組まで一類ともに厳科に処さるべきものなり。仍て下知件の如し。
天和2年5月日(1682) 奉行
1、商売人在々百姓へ借銀借米利息の儀、御国替の砌より定めらる如く、今以銀子ハ2割、米は3割たるべし。 びに米を銀に直し月借等、此以後一切これを停止す。此旨相背くにおいては、取候者も出し候者も双方厳科をこうむるべきものなり。
寛文4年11月朔日
これらの制札の文言は、前掲「因府録」によった。
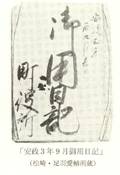 |