第2編 歴史
第3章 近世
第2節 鳥取池田家の成立
1 在方制度
大庄屋
大庄屋は時代により定員に異動があるが、河村郷(現在の東伯郡及び倉吉市のうち、竹田川・天神川以東)を里構(さとがまえ)と山中構(さんちゅうがまえ)に分け、それぞれ1名ずつ任命された時代が長いようである。当町域内の集落は、現・羽合町・泊村に属する集落と共に里構大庄屋の管轄にあった。このほかの、三朝町及び倉吉市の一部が山中構に入る。
元禄11年(1698)請免法の実施により、代官が廃止されて以来、大庄屋は年貢取り立ての全責任を負うほか、下達・上申文書の中継、訴訟の調停などの仕事に当たった。松崎町は和田氏の自分政治の地であったが、貢納のことに限って大庄屋の管轄に属した。
里構大庄屋には、現羽合町域から任命された者が圧倒的に多い。当町域内から任命されたのは次に挙げる人々である。
1、長和田村 与助
2、松崎町 市郎衛門
これは「寛永10年(1633)両国寺社領大庄屋給帳」(『鳥取藩史職制志』所収)によるものである。
松崎の市郎衛門は、寛永10年の「伯耆国河村郡之内川上村地詰帳」(川上・森田良平所蔵)の末尾に、「田畠高合百四拾七石三斗三升六合、高付は松崎の市郎右衛門仕ル」とあるのと同一人であろう。彼は大庄屋として管轄内の地詰検地の仕事に携わったとみられる。両者の任免年月は、共に不明である。
3、門田村 兵吉 任元文4年(1739)・5年のころ
免寛保元年(1741)8月1日
兵吉は屋号を向岡(むこう)本といい、現・岡本忠夫家(在鳥取市)である。大庄屋も、この時期はまだ苗字を記していない。
4、松崎町 立木宗兵衛 任宝暦4年(1754)・5年のころ
免宝暦8年(1758)から10年ごろ
立木宗兵衛は、長江・永福寺所蔵の「音田家覚書(注1)」により松崎の人と判明した。自分政治に属する松崎の町人が、在方の大庄屋に任用されたのは、特別な事情があったものと思われる。「在方諸事控(注2)」の宝暦5年10月18日の項(『鳥取県史9近世資料』所収)に、「(前略)今年年柄不宜(よろしからず)、其上、立木宗兵衛儀新役之儀故、御取立手抜(てぬかり)も有之候てハ御為不宜ニ付、納所相済候内、宗兵衛構之内ニ添役(そえやく)壱人仰付けられ候間(下略)」と、立木宗兵衛が新任ゆえ年貢の取り立てに手抜かりがあってはならないから、添役(補佐役)として長瀬村儀八郎を付けることを申し渡している。
宝暦から明和・安永年間にかけて、松崎の町年寄(後述)は2名とも立木姓であり、当時、立木一統が大きな勢力をもっていたことがうかがわれる。
(注1) 音田家覚書=仮題、表紙と共に数ページが脱落している。『羽合町史』は「音
田九郎右衛門日記」と紹介しているが、記載事項は年月日順ではなく、覚書とするのが適切である。内容は享保年間(1716〜35)から寛政9年(1797)に及び、筆録者も父子2代にわたっており、貴重な記録である(資料編101号)。
(注2) 在方諸事控=鳥取藩の民政を取り扱った在御用場の記録で、正徳5年(1715)から明治4年(1871)に及んでいる。藩の民政史研究上重要な資料であり、『鳥取県史近世資料』の9巻から13巻までに集録されている。以下「諸事控」と略称する。
 |
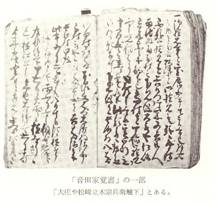 |