第2編 歴史
第1章 原始・古代
第5節 奈良・平安時代
1 律令制下の郷土
郡司と郡衙
郡司は、国司の支配下にあって、律令制の国家施策と民衆との接点、という重要な役割を担っていた。郡司には、大化改新前の国造級の地方豪族が優先的に任用されたといわれる。その場合、かつての在地首長が持っていた宗教的権威はなくなり、徴税などの純粋な地方行政官として位置づけられたとされる。郡司の定員は、8つの郷から成る河村郡の場合、「大領」、「少領」など4人と推定されている(以上『鳥取県史』)。具体的な郡司の姓名は、伯耆では史料が残っていない。
なお、律令制下で宗教的権威を掌握し、神官として一国の神社の祭祀をつかさどったのは「令制国造」と呼ばれるものであった。昭和15年に教育研究会が発行した『神祗要覧』によると、大化改新前の国造の多くは郡司に任命されたが、なかには専ら神社の祭事に奉仕する長官として、「令制国造」に補任される例もあったとする。
宮内の字「早稲田」に、「国造屋敷」、別名「神主屋敷」と称する一画がある。早稲田神社の鳥居の辺りである。このことにより、「令制国造」が倭文神社の神主として、この屋敷に居住していたとも考えられるが確証はない。
次に、郡衙(が)(郡役所)の位置については、河村郡の場合、2説がある。当時の郡名は、郡衙のあった郷の名を取っている例があり、郡衙の所在地を推定する1つの根拠とされる。『鳥取県史』は、久米郡では久米郷、八橋郡では八橋郷、会見郡では会見郷、日野郡では日野郷にそれぞれ郡衙があったと推定している。これに従えば、河村郡の場合は河村郷、すなわち現・羽合町にあったと推定される。羽合町長瀬には、国造を意味する字「国相」のほかに、国司の職階名である字「大目」、「小目」などの地名が隣接している(後述する「東郷湖周辺の条里遺構」の項を参照)。いずれも直接には郡衙のあったことを証明するものではないが、『羽合町史前編』などは、この辺りを郡衙所在地に比定している。
これに対して、羽合平野は低平で洪水被害を受けやすく、郡衙位置としては適当でないとする説がある。この説では、郡衙を野方廃寺のあった舎人郷の野方、あるいは古瓦が出土した多駄郷の久見付近に比定する(岩永実『鳥取県地誌考』など)。野方・久見とも、小字地名などにはその痕跡を確かめることはできないが、郡衙のあった可能性は十分考えられる。
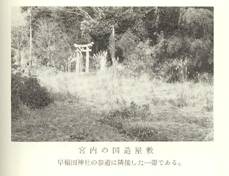 |