第2編 歴史
第1章 原始・古代
第4節 古墳時代
2 町内の概観
土師器と須恵器
古墳時代によく使用された土器に、土師器と須恵器の2種類がある。土師器は、弥生式土器の流れをくみ、古墳時代を通じて使用されている。摂氏850度前後で焼かれたと推定され、色は黄褐色で、文様はほとんど見られない。日常品として広く普及し、種類は坏(つき)、高坏、壺(つぼ)、甕(かめ)、甑(こしき)、鉢、器台などがある。一方の須恵器は、古墳時代の後期から使われ始める。摂氏1000度以上で焼かれ、色は灰色か灰黒色をし、土師器より堅く、たたくと金属音に近い音がする。朝鮮土器とも呼ばれるように、大陸から伝わった方法で製作された。高坏・壺など容器の種類は土師器と同様である。古墳時代後期から平安時代にかけて各地の窖窯(あながま)で作られた。その焼成技術は、後の瀬戸焼きや備前焼きなどの母体になったとされる。
土師器、須恵器とも、時代判定の役割をする重要な遺物である。山陰地方でも、土師器は集落跡、須恵器は窯跡出土のものを中心に、編年の研究が進められている。
町内では、北山古墳の土師器をはじめ、重要な古墳から土師器や須恵器が出土している。また前掲『東郷町内遺跡分布調査報告書』は、古墳以外の土器散布地として、土師器のみ30か所、土師器と須恵器26か所、須恵器のみ7か所を挙げているので参考にされたい。なお、須恵器のみ出土した遺跡の1つが、埴見窯跡群である。
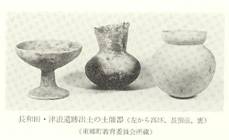 |
 |