第1編 自然と地理
第1章 自然と環境
第6節 植物
1 町内の特色
概説
町内の植物は、水平分布の区分からすると暖帯林に属している。スダジィイ・ヤブツバキに代表される照葉樹(常緑広葉樹)林が広く分布する地域である。これは、日本海に近く、四季の温度差が比較的少ない温暖な気候のためである。主な照葉樹では、スダジイ・ヤブツバキのほか、シラカシ・カゴノキ・ヤブニッケイ・アカガシ・ウラジロガシ・シロダモ・タブノキ・サカキ・トベラ・ヒメユズリハ・カクレミノ・モチノキ・アリドウシなどが挙げられる。このほか常緑のイタビカズラ・キヅタ・テイカカズラのようなつる植物も多く見られ、暖帯性植物区の特色を示している。また、落葉広葉樹のムクノキ(注)・ケヤキコナラ(ハアソ)・クリ・リョウブ・カシワ・エゴノキ(ツナイ)・ヤマボウシ(イッキ)・センダンなどが混生し、アカマツ・スギ・ヒノキの針葉樹と、さらにクロモジ・ハイイヌガヤ・クマシデ・ナツツバキなど温帯性の植物も見られる。これらは北方、ないし寒地性の植物である。かつて、世界的に寒冷をもたらした氷河時代の名残とも考えられる。
このように、暖帯性の植物を主体に、北方系の植物も混生しているのが本町の特色といえよう。
昭和58年に、植物に詳しい森本満喜夫(倉吉市)が調査した町内の植生図を別添「付図」に収録した。10年前の別の調査結果に比べて、果樹園が増加していること、また、コナラ・クリの混交林やイヌシデ・ムクノキ・ケヤキなど高木の広葉樹林が、アカマツ・スギなどの人工林に変わり、自然の植生が滅少しつつあることが分かる。以下、町内の特徴的な植生を2、3紹介する。
| (注) | ムクノキの自生は、県中部では東郷町のほかには見られない貴重なものである。倉吉市内・三朝町内など近隣町村の寺院、神杜の境内に現在ある巨木のムクノキは、町内の自生木を移植したものと推察される。 |
 |
 |
|
| ヤマボウシ |
アカガシ |
|
 |
 |
|
| ムクノキ |
センダン |
|
 |
 |
|
| エゴノキ |
ヤブツバキ |
|
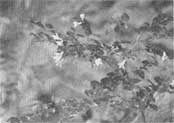 |
||
| アリドウシ |
||
| (写真はいずれも倉吉市・森本満喜夫提供) | ||